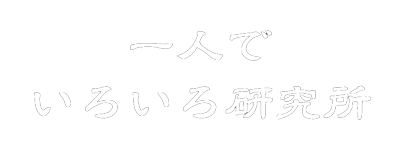ストックオプション制度というのは、役員或いは社員に対して、ボーナスに代え自社の株式を将来何年か後に特定の価額で購入できる権利(ストックオプション)を付与する制度です。原則、課税対象となります。制度の概要と税金の取り扱いについて概説します。
ストックオプション制度の概要
「ストックオプション制度」というのは、会社が、取締役や執行役といった役員或いは従業員や使用人に対して、ボーナスに代え自社の株式を将来何年か後に特定の価額で購入できる権利(オプション)を付与する制度を指します。
但し、ストックオプションの付与が決議された当日に、市場の株価以下で購入でき、かつ、すぐに無条件で売却できる権利ではありません。
何年か後に、よくあるのは2年以降、現在よりも高い株価に設定された価額で購入できる権利のことです。
そのオプションを行使する際、株式市場での株価が、当初に定められた株価である「権利行使価額」を上回っていれば、売却益を実現できることになります。
取締役や執行役といった役員或いは従業員や使用人が、会社の業績を上げることに努力すれば、当然、株価が上昇し、売却益が増えるはずです。
ストックオプションは、業務を行う上でのモチベーションにつながります。
株価の上昇は、株主の利益にも直結しています。
株主としても、業績向上につながるストックオプションは、ウエルカムとなっています。
ストックオプション制度の解説項目
ストックオプション制度について、以下の観点から概説します。
1.ストックオプションに関する原則的な課税の考え方(税制非適格ストックオプション)
1.1 ストックオプションの具体例
1.2 ストックオプション取得時
1.3 権利行使時
1.4 株式の売却・譲渡時
2.税制適格ス有数オプションに関する課税の考え方
2.1 ストックオプションの具体例(上記1と同じ)
2.2 ストックオプション取得時
2.3 権利行使時
2.4 株式の売却・譲渡時
3.人事戦略としてのストックオプションと留意点
1.ストックオプションに関する原則的な課税の考え方(税制非適格ストックオプション)
ストックオプションは、原則、「課税対象」となります。
但し、タイミングにより違いがあるほか、特例として、課税タイミングの繰り延べが認めれられています。
この点については、2で概説します。
税法上、原則としてどのように扱われるか、以下、概説します。
1.1 ストックオプションの具体例
• 2年経過した後5年間、権利行使価額として1000円を払い込めば、1000株取得できるオプションを取得
• ストックオプションを取得した当日の1株当たりの株価は800円
• 2年後、ストックオプションの権利を行使できるようになった日の1株当たりの株価が2000円であったので、権利行使し、1株当たり1000円を払い込み1000株を取得
• その後、株価が上昇し、1株当たり3000円で売却
1.2 ストックオプション取得時
この時点で、付与者の制限や譲渡制限あるいは行使期間の制限等があれば、課税されません。
上記の例から言えば、あくまでも、2年を経過した後の5年間の時点で、ストックオプションの権利行使の権利を得ただけです。
将来、会社が存続するどうかもわかりません。
当然、業績が上がり、株価が行使価格を上回る保証もありません。
1.3 権利行使時
1株当たり2000円の株式を1000円で1000株購入できるわけですから、権利行使を行った時点で、本来2百万円のものを1百万円で入手し、2百万円‐1百万円=1百万円の益が発生します。
但し、実現しているわけではありません。
とはいえ、この1百万円は、会社が経済的利益を役員や従業員に提供したものと理解し、他の給与所得と合算され課税対象とするというのが、税法上の原則的な考え方です。
もし、国税に係る所得税率が40%であれば、住民税10%と合わせ、ストックオプションの権利行使時に50%の税金がかかります。
実際に、売却や譲渡しているわけではないので、資金的に余裕がない場合もあると予想できます。
課税タイミングの繰り延べが認めれる理由の一つとなっています。
源泉徴収の手続きが行われていない場合、含み益がどれほどか査定できるような書類を添え、「確定申告」が必要となります。
1.4 株式の売却・譲渡時
株式の売却や譲渡時に、購入価格よりも高く売却あるいは譲渡できれば、利益、いわゆるキャピタルゲインを実現できます。
権利行使時に所得扱いを受けた場合、購入金額は1株当たり2000円となるので、売却時或いは譲渡時1株当たりの株価が3000円であれば、1000円@1000株、1百万円のキャピタルゲインが得られます。
2023年1月時点で、総合分離課税が適用される証券口座で売買していれば、1百万円×20%=20万円の源泉徴収税が課せられます。
源泉徴収をしていない場合、実現益がどれほどか査定できるような書類を添え、「確定申告」が必要となります。
NISA口座の場合、投資枠が600万円で5年間、120万円の非課税枠があるようです。
この点、銀行や証券会社でご確認下さい。
2.税制適格ス有数オプションに関する課税の考え方
条件が整えば、課税のタイミングの繰り延べが認めれられています。
税法上、どのように扱われるか概説します。
2.1 ストックオプションの具体例(上記1と同じ)
• 2年経過した後5年間、権利行使価額として1000円を払い込めば、1000株取得できるオプションを取得
• ストックオプションを取得した当日の1株当たりの株価は800円
• 2年後、ストックオプションの権利を行使できるようになった日の1株当たりの株価が2000円であったので、権利行使し、1株当たり1000円を払い込み1000株を取得
• その後、株価が上昇し、1株当たり3000円で売却
2.2 ストックオプション取得時
この時点で、付与者の制限や譲渡制限あるいは行使期間の制限等があれば、課税されません。
2.3 権利行使時
1株当たり2000円の株式を1000円で1000株購入できるわけですから、権利行使を行った時点で、上述1のように会社が経済的利益を役員や従業員に提供したものと理解し、他の給与所得と合算され課税対象とすることも、原則可能です。
但し、実際に、売却や譲渡して、キャピタルゲインが確定しているわけではありませんので、ストックオプション制度として条件が整えば、課税タイミングの繰り延べが認められています。
税制適格ストックオプションの条件
条件ですが以下の通りとなっています。
■ ストックオプションの付与対象者
• 一定の大口株主やその特別関係者でないこと
• 自社の取締役、執行役あるいは従業員・使用人(その相続人)
• 他社の者であっても、発行済の株式総数の50%超を直接或いは関節に保有している法人の取締役、執行役あるいは従業員・使用人(その相続人)
■ 権利行使期間
• スタート:ストックオプションの付与を決議してから2年を超え
• エンド:ストックオプションの付与を決議してか10年を経過するまで
■ 権利行使価額
• ストックオプションに係る契約を行った時点の株価を上回ること
■ 権利行使価額の制限
• 権利行使価額が年間1200万円を超えないこと
2.4 株式の売却・譲渡時
株式の売却や譲渡時に、購入価格よりも高く売却あるいは譲渡できれば、利益、いわゆるキャピタルゲインを実現できます。
権利行使時に所得扱いを受けていない場合、購入金額は1株当たり1000円となるので、売却時あるいは譲渡時、1株当たり株価が3000円であれば、2000円@1000株、2百万円のキャピタルゲインが得られます。
2023年1月時点で、総合分離課税が適用される証券口座で売買していれば、2百万円×20%=40万円の源泉徴収税が課せられます。
源泉徴収をしていない場合、実現益がどれほどか査定できるような書類を添え、「確定申告」が必要となります。
NISA口座の場合、投資枠が600万円で5年間、120万円の非課税枠があるようです。
この点、銀行や証券会社でご確認下さい。
3.人事戦略としてのストックオプションと留意点
上記では、証券取引所に株式を上場しているケースを念頭にストックオプション制度を概説しました。
取締役や執行役といった役員或いは従業員や使用人にとってストックオプションに係る権利を取得することは、業績を上げ、株価の上昇に貢献できれば、自己の利益にもつながるという点でモチベーションにつながります。
重要な経営資源である人材を会社に引き留めるという観点でも意味があり、人事戦略の一つとなっています。
また、経営責任のある経営者に対して、ボーナスとして多額の現金支給よりはストックオプションの付与の方が理に適う場合も多いでしょう。
但し業績の水増しで株価を上げようとする不正な行為が発生するかもしれず、社内外の監視制度が必要になるケースもあります。
個人としてもストックオプション制度の理解と税対策は必要
ストックオプションの付与を受けた場合、従業員である個人のサイドでも、同制度の概要を正しく理解しておくべきです。
特に、会社の意図を理解すべきです。
また、権利行使時に所得扱いとなっていないかチェックが必要です。
売却や譲渡した時に、NISA口座等の非課税枠を利用したり、総合分離課税を利用して、源泉徴収を手配し、確定申告の作業を簡素化するなどの考慮も必要です。