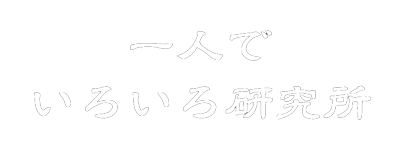お葬式やお通夜のあとは、お悔やみをいただいた方に向けて香典返しをするのがマナーです。喪主になった場合、香典返しの正しい時期や金額などを知っておく必要があります。ここでは香典返しの金額、会社からもらった際の対応などについて紹介します。
香典返しの意味
香典返しという言葉を聞いたことはあっても、どのようなものなのか、なんのために行うものなのか知らないという人は少なくありません。
喪主になった、家族が亡くなった、などの理由で葬式を行わなくてはならなくなった場合には、ほぼ確実に香典返しを用意する必要に迫られます。香典返しにどのような意味があるのかを知り、準備に戸惑わないように備えましょう。ここでは、香典返しの意味を紹介します。
いただいた香典のお返し
香典返しは、その名前の通りもらった香典のお返しとして渡すものです。お通夜やお葬式で列席者から供えていただいた金品、つまり香典に対する返礼としての意味があります。「お悔やみの気持ちを受け取りました」という、お悔やみをもらったことへの返事としての意味もあります。
香典の意味
香典は、亡くなられた方の遺族や故人にお悔やみの気持ちを表明するためのものです。そのため、お悔やみに対して感謝の気持ちを表すのが香典返しの目的になります。また、香典にはお悔やみの気持ちのほか、「葬儀費用の足しになるように」という気持ちも込められています。
香典返しを贈るまでの流れ
故人が亡くなってから香典返しを贈るまでには、お通夜・お葬式を挟み、忌明け法要を行うという過程があります。忌明け法要とは、いわゆる四十九日のことです。いただいた香典のお返しと、無事に法要が終わったことの連絡も兼ねて香典返しを贈ります。法要が終わったら香典返しを贈る、ということを覚えておくと良いでしょう。
香典返しの時期はいつ?
喪主になった場合、葬式の準備や手続きなどやらなければいけないことがたくさんあります。あらかじめ香典返しを贈る正しいタイミングを知っておくと、忙しい中でも余裕を持って準備することができます。ここでは、香典返しの正しい時期を紹介します。
四十九日が過ぎてから
香典返しは法要が無事に終わったことを報告する意味もあるので、四十九日が過ぎて忌が明けたら渡すのがマナーです。四十九日当日から1ヶ月以内が妥当な時期になります。葬儀や法要自体は、菩提寺や葬儀屋と相談しながら進めていくことになるので、段取りを決めたら早めに香典返しを準備するようにしましょう。
葬式の当日に返す場合
「当日返し」として、葬式の当日に香典返しを贈る場合もあります。その場合は、一律の値段の香典返しを贈り、高額な香典をいただいた方には後日改めて相応の品を贈ることになります。香典の値段に合わせて複数の香典返しをあらかじめ用意しておくのも一つの方法です。
香典返しを準備する時期
香典返しは初七日から忌明けまでの間に準備しておくと、余裕を持って贈ることができます。法要は命日を含めて七日目ごとに行うので、忙しい中でも香典返しの準備をするのを忘れないように気をつけましょう。
香典返しを渡すタイミング
香典返しを渡すタイミングですが、忌明けが年を越す場合には三十五日を忌明けにしてそのタイミングで渡すのが相場です。宗派や地域によって異なりますが、亡くなった日から30日から50日ほどが「忌明け」とされています。
香典返しを渡すのがあまりにも遅くなりそうな場合には、遅くなってしまったことをお詫びする内容の手紙を添えて香典返しを渡しましょう。
香典返しの金額の相場
ここでは、香典返しの金額の相場を紹介します。初めて香典返しを用意するときは、どのくらいが相場なのかがわからず悩む人が少なくありません。香典返しの金額は、地域によって相場が異なる場合があります。お葬式を行う地域や、香典返しを渡す相手に合わせてお返しの金額を決めるのがポイントです。
一般的な金額は「半返し」
いただいた香典の約半分の金額をお返しするのが香典返しのもっとも一般的な相場です。「半返し」と呼ばれており、どこの地域でも現在はこのやり方が主流になっています。
これは、昔はいただいた香典のだいたい半分ほどの金額が手元に残ったため、その分をお返ししたり寺に寄付したりしたことが始まりだと言われています。
3分の1の金額をお返しする場合
以前は、関東では半返し、関西では3分の1の金額をお返しするのが主流でした。現在では関東と関西とで香典返しの金額に明確な区別はなくなっていますが、地域によっては昔からのしきたりを大事にしている場合もあるので、不安な場合はあらかじめ親族などに相談するのが良いでしょう。
また、状況によっては3分の1の金額をお返しするのが推奨されるケースもあります。
一家の主が亡くなった・子どもが未成年だった場合
一家の働き手が亡くなった場合や、まだ子どもが小さい場合には、香典返しはもらった香典の3分の1の金額か、もしくは香典返しそのものもしなくて良いとされています。香典は「その後の生活の足しになるように」という意味も込められているので、このような場合はありがたくもらっておきましょう。
身内から多額の香典をもらった場合
親族などから5万や10万といった多額の香典をもらった場合も、香典返しは半返しでなくとも構いません。「葬式代の足しにしてほしい」という気持ちが込められたものなので、3分の1か4分の1ほどの香典返しを贈りましょう。
当日返しの場合
葬儀の当日に香典返しを行う場合、2000円から3000円ほどの金額の物を贈るのが一般的です。また、高額な香典をいただいた方には当日渡した品物と香典の半額の差額に相当する品を贈るのが妥当です。
香典返しのマナー
香典返しを行う際には、様々なマナーを守る必要があります。葬儀となると様々な決まりごとがありますが、香典返しをする場合も気をつけなくてはいけないポイントがいくつかあります。
香典返しはお悔やみの気持ちを香典で表明してくれた人に対しての感謝の気持ちを表すものです。マナーを守って贈ることができるようにしましょう。
香典返しを配送で贈る場合
香典返しを贈るときは、直接手渡しするのがマナーです。ただし、相手が遠方に住んでいたりお互いに忙しい時期だったりした場合には、配送で香典返しの品を贈るのが一般的です。お葬式に参加してくれたことへの感謝の言葉を記したお礼状や挨拶状を添えるのを忘れないようにしましょう。
香典返しの品物の定番
香典返しの品物は「後に残らないもの」を選ぶのがマナーです。「不祝儀を後に残さない」という考えがあるので、食べたらなくなるもの、お菓子や飲み物が適しています。お茶、海苔、コーヒー、砂糖などが一般的です。
食品以外であれば石鹸やタオルなどの消耗品がおすすめです。
香典返しの品としてマナー違反のもの
肉や魚など、足の早い食べ物は避けるのが無難です。近年では香典返しのカタログギフトなども充実しており、中にはブランド牛、生菓子なども香典返しとして贈ることができるようになっていますが、その場合でも消費期限や日持ちなどをきちんと確認してから贈るようにしましょう。
食べ物を配送する際の注意点
菓子や飲み物を配送で送る場合、日持ちや保存状況によって品質が変化してしまわないように注意することが大切です。冷凍保存が必要な食品の場合は特に注意が必要です。あらかじめ配達状況などをきちんと確認しておきましょう。
香典返しの贈り方のマナー
忌事には、「掛け紙」と呼ばれる紙を掛けるのがマナーです。熨斗のついた「のし紙」は慶事の時に使うものなので、香典返しには使用しません。熨斗のついていない水引のみの紙を選ぶようにしましょう。
キリスト教の香典返し
キリスト教のお葬式の場合、香典や香典返しという概念は存在しません。ただし、「御花料」のお返しとして香典返しと同じようなお返しの品を贈ることはあります。時期としては、カトリックでは「追悼ミサ」の後、プロテスタントでは「昇天記念日」の後に贈るのが一般的です。
会社から香典をもらった場合
会社から香典をもらった場合、多くの場合は会社内の規定で「福利厚生」として定められているため、会社に香典返しをする必要はありません。
ただし、会社内の所属部署、所属チームなどから連名で香典をいただいた場合にはお返しをするのが一般的です。その際、必ずしも正式な香典返しの品物を用意する必要はなく、少し高価な菓子折りなどで問題ありません。
個人の名義で香典をもらった場合
会社の同僚や会社の取引先の人から、個人で香典をもらった場合には香典返しをしましょう。そのほか、趣味のクラブや習い事の教室などから香典をいただいた場合も、お悔やみの気持ちをもらった返礼として香典返しを用意するのがおすすめです。
香典返しの知識を覚えておこう
香典返しの相場や時期には、適切な金額やタイミングがあります。お葬式を行うとなると初めてのことばかりで戸惑う人も少なくありませんが、香典返しのマナーを知っておけば後から困ることはありません。香典返しを無事に贈り、忌明けをつつがなく終えるようにしましょう。