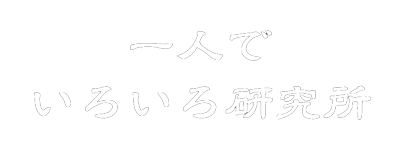「適用」の意味は?
まずは「適用」の意味から見ていきます。また、読み方が同じである「摘要」についても意味や使い方、「適用」との違いなどをあわせて紹介します。
「適用」「適用する」とは
簡単にまとめると、「適用」「適用する」とは「あてはめること」です。「適用」の「適」という字には「あてはまる」という意味があります。「用」は文字通り「用いる」「使う」という意味です。なので物事や人に対して何かの条件や事柄をあてはめて使うときに使います。
「摘要」「摘要する」とは
同じ読み方をする「摘要」「摘要する」ということばについてですが、こちらには「大事なところを抜き記すこと」という意味があり、「適用」とは意味が大きく違ってきます。
まずは文字の成り立ちですが、「摘要」の「摘」には「かいつまんで選ぶ」、「要」には「大切なこと」という意味があります。「適」の部分が違うことで全く意味が異なります。
「摘要」は、「内容を適用する」「摘要を読む」などと使うことができます。「適用」と「摘要」、読み方は一緒ですが全く違う意味なので、メールや文章にする際には変換や書き間違いのないように注意しましょう。
「適応」の意味は?
次に「適応」の意味についてです。今度は読み方は違いますが、似た意味を持つ「適合」という言葉の意味や「適応」との違いも解説していきます。
「適応」「適応する」とは
「適応」「適応する」を一言で表すと、「あてはまること」になります。「適用」「適用する」と同じく、「適応」「適応する」という言葉にも「適」という字が含まれ、「応」には「こたえる」「つりあう」といった意味があります。
そのことから「適応」はビジネスシーンでも有効で、その場の条件や環境にあてはまることを表すときに用いることができます。
「適合」「適合する」とは
「適合」には「ぴったりあてはまる」「よくあてはまる」という意味があります。「適合」という言葉を作っている「適」と「合」という漢字のどちらも「あてはめる」「合う」という意味を持つことからもわかります。
「適合」「適応」の違いについてですが、どちらにも「条件や状況にあてはまる」という意味があることから、「適合」「適合する」は「適応」「適応する」とほぼ同じであると言えます。
使い方としては、「環境に適合する」「時代に適合する」などがありますが、実はこの例文は「適応」もあてはまります。使い分けるとすれば、「適応する」は「適合する」より少しアバウトな感じで、「適合する」のほうが「ぴったり」合致するといったニュアンスが含まれています。
意味を理解できていればどちらを使っても間違いではありませんが、シーンに合わせてより適切な表現を選びましょう。
「適用」と「適応」の例文
「適用」と「適応」についての意味がわかったところで、ふたつの具体的な例文を、使用する【対象別】【場面別】で挙げていきます。実際に例文を比べて見ることで、どのように使い分けたらよいのかより理解を深めていきましょう。
【対象別】「適用」と「適応」の例文
【場面別】「適用」と「適応」の例文
【場面別】すでにある規則や条件を当てはめる場面
【場面別】考え方や行動を変える、生物が生態系を変える場面
例文ではあえて【対象別】【場面別】のふたつを紹介しました。【対象別】【場面別】とわけて考えてしまうと間違えてしまう場合もあるからです。
例えば、例文に合わせて「規則」というキーワードを対象とした場合でのみ考えてしまうと「就職先の規則に適用する」となりますが、少し違和感を感じます。正しくは「就職先の規則に適応する」です。これは例文の場面別で考えたときに「考え方や行動を変える」ことにあてはまるからです。
「適用」と「適応」のどちらを使うかは、【対象別】で選ぶか【場面別】で選ぶかの片方に縛られずに、どちらも合わせて柔軟に考えましょう。
「適用」と「適応」の違いと使い分け
例文でも紹介しましたが、「適用」と「適応」が違う意味を持ち、対象や場面で使い分けられることがわかりました。それでは改めて「適用」「適応」の違いと使い方についてまとめていきましょう。
「適用」と「適応」の違い
| 適用 | すでにある規則や条件をあてはめること |
| 適応 | 考え方や行動を変えること、生物が生態系や形態を変えること |
並べてみると違いがよく見えてきますが、「適用」と「適応」についての違いは、基本的に物事や事象に関することは「適用」、生物に関わることに対しては「適応」と考えるとわかりやすくなります。
余談ですが、ふたつの言葉の意味の違いから、それぞれに類語があることもわかります。「適用」は規則などをあてはめて用いるという意味で「施行」「運用」などに言い換えられる場面がありますし、「適応」に関しては「順応」という言葉が類語になります。
ただし「順応」については先程紹介した「適合」に比べると若干ニュアンスが変わってきます。「適応」「適合」が自ら変える・変わるという意味なのに対して、「順応」は自然と変わったという場面で用いられます。例えば「(自分自身が)新しい環境に適応した」「彼は新しい環境に順応した」と使い分けるとしっくりきます。
こちらも覚えておくと表現のバリエーションが増えるでしょう。
「適用」と「適応」の使い分け
| 適用 | あてはまる |
| 適応 | あてはめる |
どうしても使い分けに迷ったときには、「適用」は「あてはまる」、「適応」は「あてはめる」に言い換えることができるということを覚えておいてください。
「適用」は法律や規則などを特定の事項、人、事件などに対してあてはめることであり、主語は人物以外になります。対して「適応」はその場の条件・状態などによくあてはまることですので、主語は生物であり、能動的な表現になります。
例えば例文で挙げた「法律を適用する」は「法律をあてはめる」、「環境に適応する」は「環境に(自分を)あてはめる」と言い換えても違和感がありません。困ったときには一度言い換えてみてください。
「適用」「適応」を正しく使い分けましょう
いかがでしたか?一見複雑に思える「適用」と「適応」の使い分けですが、意味を理解できれば難しくはありません。今までこのふたつの言葉をなんとなく使っていた方や間違って覚えていた方は、これを機に正しい言葉を選んで使いましょう。
また、その他にも日本語には似ているようで意味が異なる言葉が数多く存在します。全てを把握するのは大変なことですが、言葉にする前に一度その使い方は合っているのか見直してみてください。