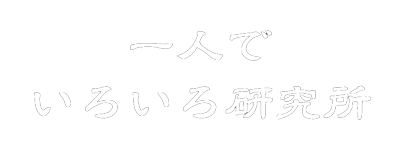相手に謝罪する際、「ご迷惑をおかけしました」を使った「ご迷惑をおかけしましたことを謝罪します」や「ご迷惑をおかけして申し訳ございません」をよく聞きます。そこでここでは、よく使われる「ご迷惑をおかけして申し訳ございません」の意味と使い方を紹介します。
「ご迷惑おかけして申し訳ございません」の意味と使い方
ビジネスシーンにおいて謝罪する機会は珍しいことではありません。自分の不注意が原因の場合もあれば、他の原因とはいえ自分が扱った案件だと理由で、謝罪に伺うこともあるでしょう。理由は何であれ、相手と良い関係を保つうえで謝罪は避けられません。
そして、そのような場合によく使われる言葉が、「ご迷惑おかけして申し訳ございません」です。直接会って口頭で謝罪する場合にも使いますが、メールやFAXなどの文書でもよく使われる言葉です。また、看板や掲示文書など、街の中でもよく見かけます。
とはいえ、「ご迷惑」の言葉の意味をきちんと理解して使っているでしょうか。みんなが使っているから、なんとなく自分も使っている方は、使い方に気を付けてください。知らずに恥ずかしい使い方をしたり、誤った敬語の組み合わせで使ってしまうこともあります。この機会に、「ご迷惑おかけして申し訳ございません」という言葉の意味を知ってください。
「ご迷惑おかけして申し訳ございません」の意味
謝罪によく使われる「ご迷惑おかけして申し訳ございません」は、「迷惑」の尊敬語である「ご迷惑」、「かけて」の謙譲語の「おかけして」、「すまない」の丁寧語の「申し訳ありません」を組み合わせた言葉です。
そして「迷惑」とは、「ある行為がもとで、他の人が不利益を受けたり、不快を感じたりすること。また、そのさま。」という意味と、「どうしてよいか迷うこと。とまどうこと。」の2つの意味があります。そのため、「ご迷惑」は、相手に対して不利益や深いな思いを与えてしまったことを指す言葉です。
また、「おかけして」には、私が迷惑をかけた、という意味が含まれており、「申し訳ありません」には相手に対して謝罪する、という意味です。
まとめると、「ご迷惑おかけして申し訳ございません」には、私が相手に対して不利益や深いな思いを与えてしまったことを、その相手に対して謝罪する、という意味であり、既に迷惑をかけてしまった場合に使います。
「ご迷惑おかけして申し訳ございません」は正しい敬語?
特に若い人にとっては、敬語の使い方は難しいものです。よく聞くフレーズだからといって、それが正しい敬語だとは限りません。また、丁寧にしようとするあまり、慣れない敬語を重ねて使って失敗することもあります。
とはいえ、「ご迷惑おかけして申し訳ございません」は、先ほどの解説したように正しい敬語です。自信を持って謝罪の場面で使ってください。
ただし、似たような表現ですが、これから迷惑をかけてしまうことが分かった場合、「ご迷惑をおかけしますが、よろしくお願いします。」という言い方をします。ビジネスシーンで聞いたことがある方も多いのではないでしょうか。
残念ながらこれは失礼な表現です。迷惑をかけると解っていながら、謝罪の言葉を伝えていません。せめて、「ご迷惑をおかけすることになり、申し訳ございません。」を使いましょう。
以下で「申し訳ありません」と「申し訳ございません」の意味の違いも確認しましょう。
「ご迷惑おかけして申し訳ございません」の例文
次に、「ご迷惑おかけして申し訳ございません」の実際に使用例を見ていきましょう。
先ほど解説したとおり、この言葉には、相手に既に迷惑をかけていて、それに対して謝罪する際に使う言葉です。そのため、いきなり「ご迷惑おかけして申し訳ございません」とは言わず、どういったことで迷惑をかけているかを示して、それに謝罪する言葉として用いるのが正しい使い方です。
次に口頭で使われるケースと、メールなどの文書で使われるケースを紹介します。
ビジネスで謝罪する場面での使い方
ビジネスに限らず、相手に迷惑をかけてしまったことへの謝罪は、直接会って伝えるのがマナーです。また、何によって迷惑をかけてしまったかが解るように、相手に伝えましょう。
文例
「この度は私の不行き届きにより、ご迷惑をおかけして申し訳ございません。」
「この度は弊社の商品に不具合が生じ、ご迷惑をおかけして申し訳ございません。」
「この度は弊社スタッフの手違いにより、ご迷惑をおかけして申し訳ございません。」
なお、口頭で謝罪した場合は、謝罪した後に今後の対応について相手と相談するのが一般的です。相手が納得する対応策を用意しておきましょう。
「ご迷惑おかけして申し訳ございません」を使ったメール
先ほど紹介したとおり、謝罪する場合は直接会って伝えるのがマナーですが、ビジネスでは相手の都合などにより、すぐに合えない場合が多々あります。そのような場合は、メールで謝罪するのが一般的です。
そして、メールで謝罪する場合は、文書として残ることから、誤りが無いように気をつけてください。また、短い文章で、具体的に書くことを心がけて、相手に情報が正しく伝わるように心がけましょう。
例文
「私の不行き届きにより、〇月〇日に納品予定だった設備「〇〇〇〇」の部品が間に合わず、ご迷惑をおかけして申し訳ございません。」
「〇月〇日に弊社より納品した型番〇〇〇〇の商品に不備があり、ご迷惑をおかけして申し訳ございませんでした。」
「〇月〇日に御社を訪問した弊社スタッフの手違いにより、ご迷惑をおかけして申し訳ございませんでした。」
また、迷惑を受けた状況によっては、相手の方も上司などに説明するため、謝罪の文書を必要とするケースもあります。そういった文書をメールで送る場合も、同じように短い文章で、具体的に書くことを心がけましょう。
ビジネスでの「申し訳ございませんでした」の誤用例などについては以下の記事をご確認ください。
「ご迷惑~」に続く他の敬語表現
先ほどご紹介したように、「ご迷惑」には、相手に対して不利益や深いな思いを与えてしまったという意味があります。これを謝罪する表現は、「ご迷惑おかけして申し訳ございません」だけとは限りません。他の言い方もあります。
次に、同じ謝罪の意味を持つ、「ご迷惑~」を使った謝罪の言葉を紹介します。
「お詫び申し上げます」と組み合わせる
「ご迷惑おかけして申し訳ございません」で使われている謝罪の言葉の「申し訳ございません」は、口頭でも文書でも使える便利な言葉ですが、軽い印象を受ける方もいます。そのため、メールなどの文書で謝罪する場合は「お詫び申し上げます」を使います。
「お詫び申し上げます」は、「あやまること、謝罪すること」の意味の「詫び」の謙譲語である「お詫び」と、「言う」の謙譲語である「申し上げます」を組み合わせた言葉で、自分が相手に謝罪する場合に使う敬語表現です。
そして、「ご迷惑」と組み合わせて、次のように使います。
例文:
「ご迷惑をおかけしたことを、お詫び申し上げます。」
また、自分がよりへりくだった表現にして、謝罪の気持ちを強調するため、「多大な」や「深く」といった形容詞を組み合わせて、次のような表現もよく使われます。
例文:
「多大なご迷惑をおかけしたことを、深くお詫び申し上げます。」
「陳謝いたします」と組み合わせる
「申し訳ございません」や「お詫び申し上げます。」と同じように謝罪する言葉に、「陳謝いたします」があります。この言葉も、「ご迷惑」と組み合わせてビジネスでの謝罪によく使われる言葉です。
なお、「陳謝」には、「事情を述べてわびること」という意味があり、この2文字だけで謝罪していることを表しています。また、「いたします」は「する」の謙譲語なので、「陳謝いたします」には、自分が相手に対して事情を述べてわびる、という意味があります。
例文:
「多大なご迷惑をおかけしましたことを陳謝いたします。」
なお、「陳謝」という言葉は、普段の会話では使いませんが、新聞などでよく見かけます。これは、公式的な表現では熟語を連続させて用いる傾向が有り、「陳謝」はこの典型的な言葉なのです。そのため、社長の名前で、会社として謝罪文書を出す場合など、公式的な表現を使う場合は、この「陳謝」を用います。
謝罪の敬語表現について詳しくは以下の記事をご覧ください。
「ご迷惑」・「お手数」・「ご不便」の違いとは
「ご迷惑おかけして申し訳ございません」は、相手に会って謝罪する場合や、メールなどの文書に書くほかに看板などでも見かけます。
例えば、工事で通路が通れない場合、その前に看板を設置して、そこに書かれているのを目にされたことがあるのではないでしょうか。そして、この場合の「ご迷惑」の相手は、工事中の通路を通る予定だった不特定の方が対象になります。
この「ご迷惑」と同じように使われる言葉に「お手数」と「ご不便」があります。例えば、「お手数をおかけして申し訳ございません」は口頭でも使いますが、設備の故障や工事中の場合、設置された看板や案内などで見かけます。また、「ご不便をおかけして申し訳ございません」も、同じように工事現場の看板などで目にします。
次に、「ご迷惑」と「お手数」や「ご不便」の違いについて、ご紹介します。
「ご迷惑」と「お手数」の違い
「お手数」は、「手数」の謙譲語であり、「手数」は「ある事をするための労力。手間。」という意味です。また、「お手数をかける」という表現の場合は、「自分のために労力を尽くしてくれた相手に対して感謝する気持ちを表す。」という意味があります。
そして、「ご迷惑をかける」は先ほども紹介したように、自分が相手に対して謝罪する際に使いますが、「お手数をかける」は、相手が何かしてくれたことに対して感謝する場合に使うのが一般的です。
例えば、工事の場所に設置する看板などで、次のような文章を使います。
文例:
「工事に伴う停止のため、他の設備をお利用ください。お手数をおかけして申し訳ございません。」
「工事が完了したので〇月〇日〇時より運用を再開しております。お手数をおかけして申し訳ございませんでした。」
なお、この例では「お手数」の代わりに「ご迷惑」を使っても変ではありません。そういった看板もよく見かけます。しかし、「ご迷惑」を看板に掲示する案内に使ってしまうと、工事に対して悪い印象を与えてしまうこともあります。この場合は「お手数」を使って、感謝の気持ちが伝えましょう。
「ご迷惑」と「ご不便」の違い
謝罪の文書として、「ご迷惑」の代わりに「ご不便」を使った表現もよく見かけます。この「ご不便をかける」で使われる「ご不便」は、「便利でないこと。都合の悪いこと。」という意味のある「不便」の謙譲語です。そのため、「かける」と組み合わせることで、私が相手に不便をかけさてた、という意味で使います。
この「ご不便」も工事の案内看板などでよく見かけます。そして、そのような場所は、工事などでいつも使える設備が使えなかったり、その場所を通れなかったりなど、相手の行動を制限する場合です。
例文:
「工事によりこの先は通り抜けできません。ご不便をおかけして申し訳ございません。」
「工事および点検のため現在使用できません。ご不便をおかけして申し訳ございません。」
なお、工事の看板に掲示するだけでなく、接客業などでお客の行動を制限せざるえない場合にも使います。「ご迷惑」を使ってしまうと、迷惑だと解っていながら、わざとやっている、と受け取る場合もあります。不特定の方を対象とする看板で掲示する場合でも使える、よりソフトな表現と言えるでしょう。
ただし、「ご迷惑おかけして」が使える場面だからといって、「ご不便をおかけして」が使える訳ではありません。使えるシーンをよく考えて使ってください。
「ご迷惑おかけして申し訳ございません」の類語・言いかえ表現
「ご迷惑おかけして申し訳ございません」は、相手に会って謝罪する場合にも、メールや文書で謝罪する場合も使いますし、看板や掲示などで不特定の方に向けても使える便利な言葉です。そのため、口癖のように使っている方も見られます。
しかし、相手を怒らせてしまった場合は、より丁寧な表現を使うべきです。また、パートナーに迷惑をかけたとしても、うまく処理してくれたのなら感謝の気持ちも同時に伝える表現を使うといいでしょう。このように、場面に合わせて、謝罪の言葉を使い分けるのが、ビジネスにおけるマナーの基本です。
ぜひ、「ご迷惑おかけして申し訳ございません」以外の謝罪の表現を使い分けてください。
「お詫びの言葉もございません」
迷惑をかけた相手が重要な顧客など、謝罪するにしても言葉を選ばなければないらいケースでは、普段使う「ご迷惑おかけして」といった謝罪の言葉では軽すぎます。かける言葉が無いくらい、最上級の謝罪の気持ちを表す言葉が、「お詫びの言葉もございません」、または、「お詫びの申し上げようもございません。」です。
ビジネスにかぎらず、初めてのミスは、多めに見てもらえることが多いことから「ご迷惑おかけして申し訳ございません」で済むことでも、そのミスが2度、3度と続くとそうはいきません。そういった、最悪のケースに使われる謝罪の言葉です。この言葉を使わずに済むように注意しましょう。
例文;
「再三ご注意を頂きながらこのような事態を招き、お詫びの言葉もございません。」
「一度ならず二度までも事故を引き起こし、お詫びの申し上げようもございません。」
なお、もちろん最上級の謝罪の言葉ですから文書やメールでも使えます。とはいえ、それに付随する文章には相手に納得してもらう文章が必要です。そのため、直接会って相手の要望に合わせて、代案を提案するのが良いでしょう。
「深謝いたします」
ビジネスにおいては、いっしょに仕事をやっているパートナーの方に迷惑をかけてしまうこともあるでしょう。そして、面倒なことを代わりにやってもらうなど、助けてもらうこともあります。
そのように方とは、救ってもらったことに対して、迷惑をかけたことを謝罪するともに、感謝の気持ちを表す言葉をかけて、より良い関係を築いていきたいものです。そして、そのような際、畏まった席やメールなどの文書で使いたい言葉が「深謝」です。「深謝」には、感謝と謝罪の両方の意味があり、心から謝罪している場合にも使う言葉です。
文例:
「ご厚意に深謝いたします」
「ご迷惑おかけして申し訳ございません」の英語表現
グローバル化が進む現在のビジネス環境では、謝罪する相手が日本人とは限りません。場合によっては、英語で謝罪することもあります。では、「ご迷惑おかけして申し訳ございません」は、英語でどう言えば良いのでしょうか。
英語には日本語の敬語にあたる言葉はありませんが、ビジネスで使われる英語特有の丁寧な表現があります。そのため、敬語の代わりに、そういった英語表現を使うのが一般的です。そして、そのような英語表現を駆使して、こちらの謝罪の気持ちを伝えましょう。
英語の丁寧な謝罪表現
「謝る」に対応する英語は「sorry」ですが、ビジネスなどのあらたまった場では「apologize」を用います。なお、この「apologize」には、「謝る、謝罪する、弁解する」といった意味がある言葉で、「sorry」よりもフォーマルな場で使われる英語表現です。
例えば。自分が相手にご迷惑をかけてしまった場合は、次の表現を使います。
例文:
「I apologise for any inconvenience I may have caused you.」
「I hope that you accept my deepest apologies.」
また、謝罪するともに、原因や対策をできるだけ早く連絡するのもビジネスマナーの1つです。例えば、メールで謝罪する場合、冒頭に謝罪の文章を短め書いて、すぐに本題に入る書き方も良い印象を与えます。そういった場合は、次のフレーズが使えます。
例文:
「I want to start by apologising.」
「sorry」を使った表現
英語でよく使われる「謝る」にあたる言葉「sorry」を使った、ビジネスでも使える表現もあります。実際に会って謝罪する場合は、「sorry」を使った方が謝罪の気持ちが伝わりやすいこともあります。
例文:
「I'm very sorry I caused this problem. It was not my intention.」
また、会話の冒頭に謝罪して、本題に入るケースもあるでしょう。そのような場合は、次のフレーズで、まず謝罪し、その後、具体的な話をするのも好印象です。ただし、メールや文書で使うのはおすすめできません。
例文:
「I am so sorry to trouble you.」
ビジネスでの謝罪は正しい言葉で誠意を示そう!
ビジネスに限らず、相手に迷惑をかけてしまった場合は、直接会って口頭で謝罪するのがマナーです。そして日本では相手に「ご迷惑をかけて」のような敬語を使うのがマナーですし、英語の場合はフォーマルな表現を使います。このように、正しい謝罪の言葉を使って誠意を示しましょう。
なお、「ご迷惑おかけして申し訳ございません」は日本語として正しい謝罪の言葉です。しかし、同じ「ご迷惑」を使う言葉には、間違えて使われる言葉もあります。
また、謝罪の程度や、ケースによっては同類後を使った方が良いケースもあり、これだけ覚えていれば良いというものではありません。ぜひ、そういった言葉といっしょに覚えておきましょう。