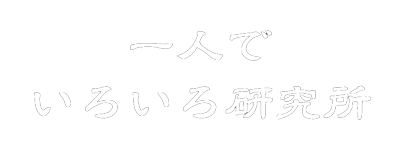7月の「時候の挨拶」「季節の挨拶」について紹介します。ビジネスシーンでとても重要な季節折々の挨拶を上旬・中旬・下旬と分けて紹介していきます。文例をもって書き出しから結びまで紹介していきますので7月の「時候の挨拶」上旬・中旬・下旬を参考にして下さい。
時候の挨拶の一覧【7月編】
7月は海開きがありとても暑い季節となります。行事としては七夕やお盆などがあります。知らない方も多いと思いますが、実は七夕は日本だけではなく海外でも行われている行事です。
そんな7月の時候の挨拶を上旬・中旬・下旬に分けて季語を用いた趣のある手紙の書き方をご紹介します。
7月の使える季語一覧
まずは季語について説明します。季語とはその季節を表す言葉になります。時候の挨拶は、この季語によって「もうこんな季節になったか」などと思わせてくれる、とても重要挨拶になります。ですので、時候の挨拶の基本は、まずこの季語から入っていきましょう。
手紙を書く時の時期や状況(天候など)により季語を使い分けていく事によって、より良い時候の挨拶になっていきます。では、どういったものが7月の時候の挨拶につかえる季語なのか、一分ですがまとめましたのでご覧ください。
| 文月 | 七夕 | 土曜鰻 | 向日葵 | 風鈴 |
| 蝉時雨 | スコール | 朝顔 | 高校野球 | 打水 |
| 海開き | 山開き | すいか | 夏休み | 青葉 |
| 半夏生 | グラジオラス | 夕顔 | 青田波 | ほおずき市 |
| 睡蓮 | 金魚 | 祇園歳 | 雷 | 夏菊 |
| 団扇 | ゲリラ豪雨 | 夕立 | 花火 | ビール |
8月の季語も使うことがある
因みに、7月であればその月の季語を使うのが理想ではありますが、挨拶に使う季語に関しては、8月の時候の挨拶で使える季語を用いることもあります。例えば「七夕」と言う季語がありますが、これは8月の時候の挨拶で使える季語になります。
なぜ、8月の時候の時候の挨拶で用いる季語が使えるのかと言いますと、これは月遅れに該当するからです。太陰太陽暦(旧暦)が使われていた時代の行事を太陽暦(新暦)で行うと日付のずれが生じます。
現在使われているのが太陽暦(新暦)となりますが、太陰太陽暦(旧暦)の年初めは、太陽暦(新暦)より約1か月遅い事になり、このずれが月遅れに該当します。
しかし、本来の時期で行事を行いたいと思われる所は、太陰太陽暦(旧暦)に近い日付で行事が行われます。これが月遅れの行事です。ですので、必ずしも7月の時候の挨拶に使える季語だけを用いて、挨拶をする訳ではない事も頭にいれておきましょう。
7月上旬に使える挨拶一覧
上旬とは1日から10日までのことを言います。7月の上旬は梅雨が明けているかいないかで、季語を使い分けながら挨拶分を書いていく必要があります。主に使われている7月上旬の時候の挨拶を紹介します。
| 時候の挨拶 | 読み方 | 意味 |
| 小夏の候 | こなつ | 日向夏の別名、4月が旬の果物だが7月の季語 |
| 小暑の候 | しょうしょ | 二十四節気の一つ、7月7日頃 |
| 星合の候 | ほしあい | 七夕・七夕の夜 |
| 梅雨の候 | つゆ | 5月~7月にかけて毎年降る雨 |
| 文月の候 | ふづき | 旧歴7月の呼び方 |
| 木槿の候 | むくげ | 7月~10月に咲く花 |
7月中旬に使える挨拶一覧
中旬とは11日から20日までのことをいいます。中旬はお盆行事があり、お祭りのように賑わう所もあれば、質素に見送る所もあります。正式には盂蘭盆会(うらぼんえ)と呼ぶそうですが、お盆を精霊に例え「ぼんさま」「ぼんさん」と呼ばれる地域もあります。
そんなお盆行事で忙しい7月中旬に使える時候の挨拶をご紹介します。暑中見舞いの時期でもありますから、それに因んだ季語を用いて挨拶するのも良いでしょう。
| 時候の挨拶 | 読み方 | 意味 |
| 暑中の候 | しょちゅう | 一年で一番暑い時期 |
| 小暑の候 | しょうしょ | 二十四節気の一つ、7月7日頃 |
| 三伏の候 | さんぷく | 陰陽五行説に基づく選日の一つ |
| 夏の夜の候 | なつのよる | 夏の夜の事 |
| 梅雨明けの候 | つゆあけ | 梅雨が明けた頃をさす |
| 冷夏の候 | れいか | 平年に比べて気温の低い夏 |
| 土用入の候 | どよういり | 土用の丑の日で有名、五行に由来する歴の雑節 |
| 打水の候 | うちみず | 玄関などに水をまく事により涼しい風をとりこむ |
| 風鈴の候 | ふうりん | 風があたる事で音色を奏でる夏の風物詩 |
| 送り火の候 | おくりび | お盆に来て頂いたご先祖様を送る行事 |
| 炎熱の候 | えんねつ | 厳しい暑さ |
7月の下旬に使える挨拶一覧
下旬は21日から末日までのことを言います。7月の下旬はちょうど祇園祭の後祭が行われます。季語としては「祇園会」や「祇園祭」も、7月の時候の挨拶に使えますので是非活用してみて下さい。
更に、7月25日は725(ナツゴ)となり夏の定番かき氷の日です。季語としては「氷水」や「かき氷」などありますが「解氷」と使われることが多いです。猛暑に用いて挨拶すれば読んだ相手も涼しくなり喜ばれます。
| 時候の挨拶 | 読み方 | 意味 |
| 大暑の候 | たいしょ | きびしい暑さ、二十四節気の一つ |
| 極暑の候 | ごくしょ | 物凄く暑い事 |
| 三伏の候 | さんぷく | 陰陽五行説に基づく選日の一つ |
| 溽暑の候 | じょくしょ | 蒸し暑い(溽)事をさす |
| 熱帯夜の候 | ねったいや | 最低気温が摂氏25度以上の夜をさす |
| 灼くの候 | やく | 直射日光が強い状態 暑くて灼ける |
| 秋近しの候 | あきちかし | 秋が近い事 夏の穏やかな時 |
| 涼しの候 | すずし | 暑い夏の中で涼しい状態をさす |
| 土用明けの候 | どようあけ | 土用の丑の日で有名、五行に由来する歴の雑節 |
| 夏の果の候 | なつのはて | 夏の終わりを表す |
| 夜の秋の候 | よるのあき | 夜が涼しくなる夏の終盤をさす |
7月ならいつでも使える挨拶一覧
7月の上旬・中旬・下旬と時候の挨拶を紹介しましたが、梅雨が明けていなかったり暑さの状態であったりなど、その時々で季語を変えていく事が必要です。そしてこの季語の後に「~の候」「~の折」「~みぎり」を付けて挨拶をするのが時候の挨拶の基本となります。
上旬・中旬・下旬と紹介した時候の挨拶以外にも、7月の時候の挨拶に使える季語はまだまだ沢山あります。色々ありすぎて選ぶのが大変という方もおられることでしょう。そうい言った方の為に、7月中ならいつでも使える7月の時候の挨拶を紹介します。
| 時候の挨拶 | 意味 |
| 盛夏の候 | 真夏、暑い時期、暑中見舞いなど全般で使用可能 |
| 炎暑の候 | ジリジリと肌が焼けるような暑さ |
| 猛暑の候 | 暑くて穏やかに過ごせない時期 |
| 厳暑の候 | きびしい暑さ |
| 酷暑の候 | 物凄く暑い |
「猛暑」「酷暑」「厳暑」「炎暑」どれが一番熱いのか?
因みに、7月の時候の挨拶の中には「猛暑」「酷暑」「厳暑」「炎暑」など、暑さを表す季語があります。どれが一番暑いのか?と疑問になるかと思いますが、基本的な定義はないようです。ニュアンスとして「炎暑」は「炎」と言う漢字を使いますので、一般的には炎暑が一番暑い様に扱われています。
手紙の挨拶文・書き出しの一覧【7月編】
書き出しとは「○○の候」の後に続く内容となります。文章の最初から本題に入りたいとは思いますが、マナーとしては安否を気遣ったり、少し小話を挟んでから本題に入る事が基本です。まずは基本となる7月の時候の挨拶に使える書き出しを紹介します。
7月上旬に使える書き出し一覧
7月上旬に使える時候の挨拶の書き出しを紹介します。7月の上旬ですと、山開き・海開き・七夕などの行事があります。年中行事も季語になる物がありますので、うまく使って書き出しをしましょう。
| 海開き山開きの知らせに心躍る季節となりました |
| 梅雨も明け早々に暑い日が続いて参りました |
| 皆様ご健勝でお過ごしのこととお慶び申し上げます |
| 小暑を過ぎて梅雨明けを待つばかりとなりました |
| 梅雨が明けず溽暑が続きますがいかがお過ごしでしょうか |
| 仕事終わりのビールがおいしい季節になりました |
| いよいよ七夕祭りが近くなりました |
7月中旬に使える書き出し一覧
7月中旬に使える時候の挨拶の書き出しを紹介します。7月の中旬ですとお盆行事やお祭りなどがあり街が賑わってきます。梅雨が明けて暑くなる時期でもありますので、相手の体調を気遣う書き出しにすると良いです。
| お盆も近づき夏祭りが盛んな季節となりました |
| 祭囃子が聞こえてくるころとなりました |
| 蝉しぐれにより眠れぬ日々が続きます |
| 今年は格別に暑く感じられます |
| 朝顔が色鮮やかに咲き誇る季節となりました |
| 今年は冷夏で過ごしやすい日々が続いております |
| お盆も終わり益々暑くなりますがいかがお過ごしでしょうか |
7月下旬に使える書き出し一覧
7月下旬に使える時候の挨拶の書き出しを紹介します。7月の下旬ですと一層日射しが強くなってきますので、相手の体調を気遣う事や、暑さを和らげるような文章にするのが良いです。
| 夜空を花火が美しく彩る季節となりました |
| もうすぐ夏休みなりますがご子息(様)はいかがお過ごしでしょうか |
| 例年にない厳しい暑さが続いております |
| 日盛りに向日葵が咲き乱れる季節となりました |
| 土用に入り益々暑い盛りとなりました |
| 風鈴の音に癒される今日この頃 |
| 連日寝苦しい夜が続いておりますがお障りなくお過ごしでしょうか |
手紙の結びの書き方【7月編】
結びとは「最後」と言う意味で、手紙やメールの最後を締めくくる文章になります。終わり良ければ全て良しと言うことわざあるように、締めくくりがうまくいかないと何事も格好が良くありません。季語を使い相手を気遣う文章で格好良く締めくくりましょう。
7月に使える結びの言葉一覧
7月の時候の挨拶に使える結びの言葉を紹介します。この時期は梅雨が明けていなければジメジメして気分が優れなかったり、梅雨が明ければ暑くて体調を崩したりします。ですので、体調を気遣うような結びの言葉にするのが良いです。
そういった気遣いをしながら、「また会いましょう」などの言葉を添えれば相手も元気が湧いてきますので、心のこもったの結びの言葉になるように心がけましょう。
| 連日うだるような暑さが続きますがお体を大切に |
| これから厳しい暑さがやってまいりますのでくれぐれもご自愛ください |
| 猛暑が続きますが夏バテなどなさらぬようご自愛ください |
| 炎暑の候お元気でお過ごしくださいませ |
| まもなく花火大会です近いうちにお会いしましょう |
| 暑さ厳しき折皆様の健勝をお祈り申し上げます |
ビジネスシーンでいつでも使える結びの言葉一覧
ビジネスにおける結びの言葉を紹介します。ビジネスシーンでは毎日メールのやり取りをされている方も少なくはないでしょう。こちらはいつでも使える結びの言葉ですので気兼ねなくご使用ください。
| 貴社の更なるご発展を心よりお祈り申し上げます |
| 引き続きご支援ご厚情を賜りますよう宜しくお願い申し上げます |
| ○○様のご健康をお祈りしつつ取り急ぎお礼申し上げます |
| 日頃はひとかたならぬご愛顧にあずかり心から御礼申し上げます |
7月の挨拶の例文【ビジネス・プライベート】
ビジネスシーンやプライベートで使える7月の時候の挨拶の文例を紹介します。ビジネスシーンにおいては堅い文章となりますが、プライベートでは上司・同僚・友人・親族と、その時々で柔らかい文章に変えていきましょう。
7月の挨拶の例文【ビジネス編】
ビジネスーンにおける7月の時候の挨拶の文例をご紹介します。
| 盛夏の候 平素は格別なご高配を賜りまして厚く御礼申し上げます。 さて、本日はご報告させていただきたい事がございましてお手紙を差し上げました。 本文 暑さが厳しい折、皆様のご健康をお祈りいたします。 |
続いて「拝啓」を入れる場合の、ビジネスシーンにおける7月の時候の挨拶の文例をご紹介します。「略儀」をつける事によって、短い文章の時にも活躍できる文例ですので是非ご活用してみて下さい。
| 大暑の候、貴社におかれましては、益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。 先日は、お忙しい所お時間をいただき誠にありがとうございます。 (つきましては)(さっそくですが)など 本文 暑くなるこれからの季節ですが、貴社の益々のご発展をお祈り申し上げます。 まずは略儀ながら書中にてお知らせします。 |
7月の挨拶の例文【プライベート編】
プライベートにおける7月の時候の挨拶の文例をご紹介します。結婚式の招待状・案内状・お礼状にも同じように時候の挨拶が使えます。因みに、招待状は「謹啓」「敬白」が一般的には使われます。案内状などは「拝啓」「敬具」でも問題はありません。
また、気軽に使える挨拶もあります。書き出しに「○○の候」などつけても良いですが、親しい仲の方ですとそこまで堅い言葉だとおかしい場合もあります。そんな時は「○○の候」ではなく、季語を用いるだけの文章でも問題ありません。
| (小暑の候) 先日、七夕祭りがありましたが行かれましたか? 今年も大いに賑わい家族みんなで楽しんできました。 本文 これから益々暑くなりますがまたお手すきの時にでも気晴らしにビールでも飲みに行きましょう。 |
夏の時候の挨拶
夏とは、6月・7月・8月の事を指します。では、夏の時候の挨拶が月毎でどのように違うのか、月毎に分けた書き出しの一覧をご覧ください。
| 6月 | 梅雨に入り溽暑が続きますがいかがお過ごしでしょうか |
| 7月 | いよいよ七夕祭りが近くなりました |
| 8月 | お盆も近づき夏祭りが盛んな季節となりました |
6月・7月は梅雨に関する季語を使う機会が多くなります。ジメジメとした中で、相手の体調を考えながら文章を考えていきます。6月の下旬のの父の日や、7月上旬の七夕などの行事を組み合わせると尚良いでしょう。
7月・8月は七夕・お盆・暑中お見舞いなどに関する季語を使う機会が多くなります。特に七夕やお盆は月遅れの行事もありますので、挨拶を送る相手の地域が、いつ行事を行うか確認をしておく必要がありますので気を付けましょう。
暑中お見舞い
7月は暑中お見舞いと言うものがあります。暑中お見舞いとは、暑い夏にお世話になった方などへ、安否確認を兼ねて家を訪問したり、手紙やメールを出すことです。感謝の気持ちや体を労って贈り物もします。
時期は色々ですが、一般的には梅雨明けや小暑(7月7日)から立秋(8月7日)までに行われます。7月の時候の挨拶では、この暑中お見舞いがとても重要なものとなりますので、よく理解しておきましょう。
暑中お見舞いの文例一覧
梅雨が明けた後に使える暑中お見舞いの文例を紹介します。
| 暑中お見舞い申し上げます。 梅雨が明け、日々酷暑が増しております。 体調はお変わりございませんでしょうか。 本文 まだまだ暑い日が続きますが、○○様も体調には気をつけてお過ごしください。 令和○○年 盛夏 |
相手がこちらの安否を気にしている時の文例を紹介します。
| 暑中お見舞い申し上げます。 暑い日が続きますが、元気でお過ごしでしょうか。 私共は元気に過ごしております。 本文 これから、益々厳しい暑さがやってまいりますがくれぐれもご自愛ください。 令和○○年 盛夏 |
ビジネスシーンで使える文例を紹介します。
| 暑中お見舞い申し上げます。 厳暑の候、益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。 本文 今後とも変わらぬお引き立ての程、よろしくお願い申し上げます。 令和○○年 盛夏 |
自分なりの時候の挨拶
7月の時候の挨拶を上旬・中旬・下旬と分けて紹介してきました。7月はお盆・お祭り・暑中見舞いなど年中行事が沢山ある中、手紙やメールのやりとりが多く非常に大変な時期です。
そんな中、風情ある時候の挨拶をすることで、自分の身を引き締めることもできますし、気遣う文章を送れば相手も元気が湧いてきます。時候の挨拶の文例を参考に、書き出しや結びを工夫しながら、自分なりの時候の挨拶を身に着けていきましょう。