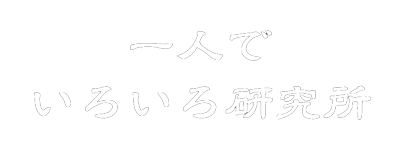近年、SNSは個人から企業まで幅広く活用され、情報発信や集客の重要なツールとして欠かせない存在になっています。その中でも、X (旧Twitter) は特に拡散力が高く、短い文章で多くの人にメッセージを届けられる便利なプラットフォームとして、多くのユーザーが日々情報を発信しています。しかし、フォロワーを増やし続けたり、継続的に質の高い投稿を行うのは簡単ではありません。忙しい日々の中で「何をポスト (ツイート) すればいいのかわからない」「毎日投稿しようとしてもネタが尽きてしまう」と悩んでいる方も多いのではないでしょうか?
特にビジネスでXを活用している場合、投稿の一つ一つが集客や信頼の積み重ねになります。そのため、「更新を止めたくないけれど、考える時間が足りない」「SNSの運用だけで手一杯になってしまう」という負担を感じる方も少なくありません。そんな悩みを解決するために役立つのが、AIの力を活用した自動化です。
本記事では、ChatGPTとMakeという2つのツールを活用し、Xの投稿を完全自動化する方法をご紹介します。この自動化を取り入れることで、投稿ネタに悩む時間を減らし、ポストの作成から投稿までをAIに任せられるようになります。さらに、一定の頻度で自動的にポストを投稿することで、継続的な情報発信が可能になり、フォロワーとのつながりも保ちやすくなります。
SNS運用の負担を軽減しながら、効果的に情報発信を続けたい方にとって、この方法は大きな助けになるでしょう。この記事を参考に、AIを上手に活用して、SNSの運用効率を飛躍的に向上させてください。
ChatGPTとMakeを使ってXを自動化するメリット
Xの自動化を取り入れると、日々のSNS運用が驚くほど効率的になります。特に忙しい方や、投稿を続けることに負担を感じている方にとって、大きな助けになります。ここでは、ChatGPTとMakeを使ってXを自動化するメリットについて、初心者の方にもわかりやすく解説します。
まず、最大のメリットは「投稿作成の時間を削減できる」ことです。これまで、何を投稿するか考えたり、文章を練り直したりするために、多くの時間を費やしていた方も多いのではないでしょうか?ChatGPTを使えば、あらかじめ指示を与えておくだけで、AIが自動で文章を生成してくれます。これにより、「今日はどんなポストをしよう?」と悩む時間を大幅にカットできます。ビジネスのためにXを活用している場合でも、時間の節約は大きなメリットになります。
次に、「継続的な情報発信ができる」という点も見逃せません。SNSの運用で大切なのは、定期的に情報を発信し続けることです。しかし、忙しい日々の中で毎日投稿し続けるのは簡単ではありません。自動化ツールを使えば、事前に投稿スケジュールを設定しておくだけで、AIが自動的にポストを作成し、投稿してくれます。これにより、情報発信が止まることなく、フォロワーとの関係を維持し続けることができます。
さらに、「多様なコンテンツを自動生成できる」のも大きな魅力です。ChatGPTは非常に柔軟で、さまざまなジャンルのポストを作成できます。たとえば、最新ニュースの要約、業界トレンドの紹介、モチベーションを高める名言の投稿、教育的なヒントなど、指示次第で幅広いコンテンツを作ることが可能です。これにより、フォロワーに飽きさせず、常に新鮮で価値のある情報を提供できます。
また、「Xの自動化はマーケティング活動を強化する」というメリットもあります。定期的に役立つ情報を発信し続けることで、フォロワーとの信頼関係を築きやすくなります。信頼性のあるアカウントは、フォロワーが増えやすく、拡散力も高まります。特に、ビジネス目的でXを運用している場合、信頼の積み重ねは売上や集客に直接影響するため、自動化の効果は非常に大きいです。
加えて、「人間的なエラーを減らせる」という利点もあります。手動で投稿を続けていると、誤字脱字や投稿忘れなどのミスが発生しがちです。しかし、ChatGPTとMakeを使った自動化では、事前に設定した内容に基づいてAIが正確にポストを作成し投稿するため、こうしたヒューマンエラーを最小限に抑えられます。
最後に、「アイデアの枯渇を防げる」という点も重要です。毎日ポストを続けると、「ネタが尽きてしまった」「何を投稿すればいいのかわからない」と悩むことがあります。しかし、ChatGPTは与えられたテーマやキーワードに基づいて、無限にアイデアを生成できます。これにより、クリエイティブな発信を継続的に行うことができます。
このように、ChatGPTとMakeを活用したXの自動化には、多くのメリットがあります。投稿作成の手間を削減し、継続的な発信を可能にするだけでなく、多様なコンテンツの生成やマーケティングの強化など、SNS運用の質そのものを向上させてくれます。初心者の方でも簡単に始められるので、ぜひ導入してみてください。
ChatGPTとMakeの準備と基本設定方法
ChatGPTとMakeを使ってXを自動化するためには、まずこれらのツールを正しくセットアップする必要があります。特に初心者の方にとって、設定の手順が複雑に感じることがあるかもしれませんが、順を追って丁寧に解説するので安心してください。これから説明する手順をひとつずつ進めれば、誰でも簡単に自動化をスタートできます。
最初に行うのは、Makeのアカウント作成です。Makeは「ノーコードツール」と呼ばれるもので、専門的なプログラミングの知識がなくても、複数のアプリケーションを連携し、自動化の仕組みを作れる便利なツールです。公式サイト(https://www.make.com/)にアクセスし、無料アカウントを作成しましょう。アカウント作成時には、名前やメールアドレスの登録が必要になります。
アカウントの作成が完了したら、次はログインを行います。ダッシュボード画面が表示されるので、ここから自動化のシナリオを作成していきます。ダッシュボードとは、Makeの中心となる管理画面のことで、ここからすべての自動化の流れを制御できます。
次に必要なのは、ChatGPTをMakeで使用するための「OpenAI APIキー」の取得です。ChatGPTはOpenAIが提供するAIツールで、このAPIキーがなければ外部ツールと連携することができません。APIキーを取得するためには、OpenAIの公式サイト(https://openai.com/)にアクセスし、アカウントを作成してからダッシュボードにログインします。
OpenAIのダッシュボードから「API Keys」のセクションに進み、「Create new secret key」というボタンをクリックすると、新しいAPIキーが生成されます。このAPIキーは非常に重要な情報なので、他人に知られないよう注意してください。また、APIキーは一度生成すると再表示されないため、取得時にメモ帳などに保存しておくことをおすすめします。
APIキーを取得したら、次はいよいよMakeでの初期設定に移ります。Makeのダッシュボードに戻り、「シナリオ」タブをクリックしてください。「シナリオ」は、複数のアプリケーションをどのように連携させるかを定義する作業エリアです。ここで「Create a new scenario」というボタンをクリックし、新しいシナリオを作成します。
シナリオの作成画面では、画面中央に「+」のアイコンが表示されます。ここをクリックし、検索ボックスに「ChatGPT」と入力します。すると、ChatGPTのモジュール(アプリケーションの連携パーツ)が表示されるので、選択してください。
次に、ChatGPTの接続設定を行います。ChatGPTのモジュールを選択すると、「APIキー」と「OpenAIアカウントID」の入力画面が表示されます。ここに、先ほどOpenAIの公式サイトで取得したAPIキーを貼り付けましょう。これでChatGPTとの接続が完了します。
次のステップでは、ChatGPTにどのようなポストを作成させるか、具体的な指示(プロンプト)を設定します。プロンプトとは、「AIにどういう文章を作成してもらうか」を伝える指示文のことです。例えば、「最新ニュースを141文字以内で要約してポストしてください」というように、日本語で直接指示を与えることができます。
プロンプトを入力したら、テスト実行をしてみましょう。テスト実行を行うと、ChatGPTが実際にポストを生成してくれます。この時点では、まだXへの投稿は行われず、テキストの生成だけが確認できます。ここで問題なく投稿文が生成されることを確認できたら、次のステップへ進みます。
次に、ChatGPTで生成されたポストを自動的にXへ投稿するための設定を行います。再びMakeのシナリオ作成画面に戻り、先ほどの「+」ボタンをクリックしてください。今度は「Twitter」または「X」と検索し、「Create a Tweet」というモジュールを追加します。
このモジュールは、ChatGPTで作成されたポストを実際にXへ投稿する役割を果たします。次に、Xアカウントとの連携を行います。モジュールをクリックすると、Xのログイン画面が表示されるので、自分のXアカウントでログインし、アプリ連携を許可します。
Xアカウントの連携が完了したら、「ポストの内容」の項目に、先ほどChatGPTで生成したポスト文を指定します。これで、ChatGPTで作成したポスト文がXに自動投稿される準備が整いました。
最後のステップは、ポストの自動投稿スケジュールの設定です。スケジュールの設定では、「どのくらいの頻度で自動投稿するか」を決めます。例えば、「1時間ごとにポストする」「毎日10時にポストする」といった設定が可能です。
スケジュール設定が完了したら、シナリオを「オン」にして、自動化の仕組みを有効化します。これで、ChatGPTとMakeを使ったXの自動化設定が完了です。
ここまでの手順をまとめると、まずMakeでアカウントを作成し、OpenAIのAPIキーを取得しました。その後、MakeのシナリオでChatGPTとXを連携し、プロンプトを設定してポストの自動生成と投稿までの流れを作成しました。
この設定により、手動で投稿内容を考える手間が省けるだけでなく、定期的な投稿が自動で行われるため、フォロワーとのエンゲージメントも向上します。これからXの運用を効率化したい方にとって、非常に有効な方法です。ぜひこの自動化手法を取り入れ、SNSマーケティングをさらに効果的に進めてみてください。
Xアカウントとの連携と自動投稿設定
ChatGPTとMakeの準備が整ったら、次のステップはX(旧Twitter)アカウントとの連携です。これを行うことで、ChatGPTが自動生成したポストを、Makeを通じて自動的にXに投稿できるようになります。ここでは、初心者の方でも迷わず設定できるように、わかりやすく手順を説明していきます。
まず、Makeのダッシュボードを開きます。ここで、既存のシナリオを開くか、新しいシナリオを作成しましょう。シナリオとは、異なるアプリケーション同士を連携させる自動化の仕組みのことです。新しいシナリオを作成する場合は、画面右上にある「Create a new scenario」をクリックしてください。
シナリオ作成画面に移動すると、中央に大きな「+」ボタンが表示されます。ここをクリックし、連携させるアプリケーションの検索画面を表示します。次に、「Twitter」または「X」と検索し、候補の中から「Create a Tweet」というモジュールを選択します。このモジュールが、Xへのポスト投稿を自動化するためのパーツになります。
モジュールを選択すると、Xのアカウント認証画面が表示されます。ここで、自分のXアカウントにログインし、Makeとの連携を許可する必要があります。アカウント認証画面では、「アプリ連携を許可する」というボタンが表示されるので、これをクリックして先に進みます。認証が成功すると、Makeの画面に戻り、アカウント連携が完了した状態になります。
次に、生成されたポストの内容をXに投稿できるよう設定していきましょう。Xのモジュール内に「ポストの内容」という入力フィールドがあります。このフィールドには、前のステップでChatGPTが生成したテキストを指定します。これにより、ChatGPTで作成したポスト文がそのままXに投稿されるようになります。
ここで重要なのは、正しく連携ができているかの確認です。Makeでは、すべての設定を終えた後に「テスト実行」が可能です。ポストの自動投稿設定が正しく行われているか、テスト実行ボタンを押して確認してみましょう。テストを行うと、ChatGPTで作成されたポストがXに自動的に投稿されます。投稿が成功すれば、設定は問題ありません。
次に、自動投稿の頻度を設定します。Makeでは、ポストの投稿スケジュールを細かく調整できます。シナリオの画面にある「スケジュール」オプションをクリックし、投稿の頻度を決めましょう。例えば、「毎日1回投稿」「1時間ごとに投稿」「週に3回投稿」など、自由にスケジュールを設定できます。
スケジュール設定を行うことで、ChatGPTが自動生成したポストが、指定した時間に自動的にXに投稿されるようになります。これにより、手動で投稿を行う必要がなくなり、投稿の手間が大幅に削減されます。
このとき注意が必要なのは、投稿頻度を高くしすぎないことです。過度に頻繁な投稿は、フォロワーにとってスパム的に見えてしまう可能性があり、アカウントの信頼性を損ねる場合があります。適切な投稿頻度を設定し、フォロワーとの関係を維持しながら情報発信を続けましょう。
さらに、自動投稿の内容をカスタマイズすることも可能です。ChatGPTのプロンプトを調整することで、投稿内容をより個性的で魅力的なものに変更できます。例えば、「最新ニュースの要約」だけでなく、「日替わりのモチベーション名言」「商品紹介文」「フォロワーへの質問形式の投稿」など、工夫次第で幅広い投稿パターンを作成できます。
また、ハッシュタグの自動生成も設定できます。ChatGPTのプロンプトに「関連するハッシュタグを含めてください」と記載すれば、AIが自動的にハッシュタグを提案し、ポストに追加してくれます。これにより、より多くのユーザーにポストが届きやすくなります。
ここまでの設定が完了したら、シナリオ全体を保存し、「アクティブ」に切り替えましょう。これで、自動化シナリオが稼働し始め、指定した時間に自動でポストが投稿されるようになります。
Xアカウントとの連携と自動投稿設定を完了したことで、日々のSNS運用の負担が大幅に軽減されます。これまでポスト内容を考えたり、投稿する時間を気にしていた手間から解放されるだけでなく、継続的で効果的な情報発信が可能になります。
さらに、この自動投稿の仕組みは、SNSマーケティングにも大きく貢献します。定期的に有益な情報を発信し続けることで、フォロワーの信頼を高め、アカウントの成長を促進できます。また、ターゲット層に合わせた投稿内容を工夫することで、エンゲージメント率の向上も期待できます。
最後に、自動化の運用状況を定期的にチェックすることをおすすめします。自動化は非常に便利ですが、設定ミスやポスト内容の一貫性を見落とす可能性もあります。定期的にMakeのダッシュボードを確認し、意図した通りにポストが投稿されているかチェックしましょう。
Xアカウントとの連携と自動投稿設定は、初心者の方でも簡単に始められる強力なツールです。ChatGPTとMakeを組み合わせることで、SNSの運用を劇的に効率化し、より効果的なマーケティング活動を実現できるでしょう。ぜひ、この自動化手法を取り入れ、Xの活用を一歩先に進めてみてください。
ChatGPTでのポスト内容のカスタマイズ
ChatGPTは非常に柔軟で、高度な文章生成能力を持つツールです。そのため、X(旧Twitter)の自動投稿に使用する場合、ポストの内容を自由自在にカスタマイズできます。単に自動でポストを生成するだけでなく、プロンプト(指示文)の工夫次第で、投稿内容の質を高めたり、ターゲット層に合わせた表現が可能になります。
ポストを自動化すると聞くと、「画一的で機械的な投稿になってしまうのでは?」と不安に思うかもしれません。しかし、ChatGPTは非常に柔軟に文章を生成できるため、細かい設定を行えば、人間らしい魅力的な投稿を作成できます。ここでは、初心者の方にもわかりやすく、ポスト内容をカスタマイズする方法を詳しく解説します。
まず、ChatGPTでポスト内容をカスタマイズする第一歩は、明確なプロンプトを設定することです。プロンプトとは、ChatGPTに「どのようなポストを作成するか」を伝えるための指示文です。このプロンプトが具体的であればあるほど、出力されるポストの質は向上します。
例えば、「最新のAIニュースを要約して投稿してください」といった具体的な指示を出すと、ChatGPTは自動的に最新情報を要約し、簡潔なポストを作成してくれます。同様に、「ポジティブな名言を生成してください」「ビジネスパーソンに向けた励ましの言葉を投稿してください」などの指示も効果的です。
また、テーマを限定してポストさせることもできます。特定のジャンルや業界に特化した投稿を続けることで、アカウントの専門性を高め、フォロワーの関心を引きやすくなります。例えば、「デジタルマーケティングに関する情報をポストしてください」や「健康に関する豆知識を投稿してください」といったプロンプトを設定することで、よりターゲットに合った投稿を生成できます。
次に、ポストのトーン(文体)の調整方法について説明します。ChatGPTは、フォーマルな表現からカジュアルな語り口まで、幅広い文体で文章を生成できます。そのため、プロンプトに「フレンドリーな口調で」「ビジネスライクに」「親しみやすく」などの指示を加えることで、ポストの雰囲気をカスタマイズすることが可能です。
たとえば、ビジネス向けのアカウントであれば、「専門的で信頼感のある表現でポストしてください」と指示すれば、堅実でプロフェッショナルな投稿が生成されます。一方で、個人アカウントやライフスタイル系の発信であれば、「親しみやすく、絵文字を使ってください」と指示することで、より気軽で共感を呼びやすいポストが作成されます。
さらに、ポストの長さも調整可能です。Xの文字数制限に合わせて、「140文字以内で」「280文字以内で」と明示的に指定することで、適切な長さの投稿が生成されます。長すぎず短すぎず、バランスの取れたポストを作成するためには、この文字数指定が非常に重要です。
次に紹介するのは、ハッシュタグの自動生成です。ハッシュタグは、投稿の拡散力を高めるために非常に重要な要素です。ChatGPTに「関連するハッシュタグを5つ含めてください」と指示すれば、生成されたポストに自動的にハッシュタグを付けることができます。これにより、検索結果での露出が増え、より多くのユーザーにポストが届く可能性が高まります。
例えば、「最新のマーケティングトレンドを解説してください。関連するハッシュタグを3つ含めてください」と指示すると、生成されるポストには「#マーケティング #SNS活用 #デジタル戦略」といったハッシュタグが自動的に含まれるようになります。
また、複数のポストを自動生成して、スレッド投稿を行うことも可能です。スレッド投稿とは、一つのテーマについて複数のポストを連続して投稿する方法です。これを活用すれば、長文で説明が必要な内容も複数のポストに分割して伝えられます。
ChatGPTでスレッド投稿を作成する場合、「3つのポストに分けて解説してください」や「ステップバイステップで説明してください」と指示すると、複数のポストが生成されます。これをMakeで設定すれば、スレッド形式での自動投稿も簡単に実現できます。
もう一つのカスタマイズ例として、フォロワーとのエンゲージメントを高めるための質問形式のポストがあります。質問形式の投稿は、フォロワーの反応を引き出すのに効果的です。ChatGPTに「フォロワーに問いかける形で投稿してください」と指示すれば、「皆さんのおすすめの読書法を教えてください!」といった投稿が生成されます。
このように、ChatGPTの柔軟性を活かせば、ポスト内容のカスタマイズは無限に広がります。投稿内容を工夫し、ターゲット層に響くポストを自動で生成できるようにプロンプトを最適化していきましょう。
ポスト内容を自動化する場合でも、完全にAI任せにするのではなく、定期的に投稿内容を見直すことが大切です。特に、ビジネス向けアカウントの場合は、投稿の一貫性やブランドメッセージに注意を払いましょう。ChatGPTの出力結果を時折確認し、必要に応じてプロンプトを調整することで、より質の高い自動化が実現できます。
まとめると、ChatGPTを使ったポストのカスタマイズ方法には、プロンプトの明確化、ポストのトーン調整、文字数の指定、ハッシュタグの自動生成、スレッド投稿、質問形式の活用など、さまざまな工夫が可能です。これらの方法を活用することで、Xの自動投稿がより魅力的で効果的なものになります。
自動化を最大限活用するための注意点
X(旧Twitter)の自動化は、SNS運用の負担を大幅に軽減し、継続的な情報発信を可能にしてくれる便利な手法です。しかし、ただツールを導入するだけでは効果的な運用とは言えません。自動化の仕組みを正しく使いこなすためには、いくつか注意すべきポイントがあります。これらを意識せずに運用してしまうと、フォロワーの信頼を失ったり、最悪の場合アカウントの凍結リスクにもつながります。
まず最も重要なのが、自動ポストの頻度です。投稿の頻度が高すぎると、フォロワーにとってスパム的に感じられることがあります。特に、1時間に何十回も投稿するような過剰な自動化は避けるべきです。Xのアルゴリズムは過度な投稿を行うアカウントをスパムとみなす可能性があり、凍結や一時停止の対象になることがあります。
自動化の目的は「効率的にフォロワーとつながること」であり、「フォロワーを疲れさせること」ではありません。そのため、1日1〜3回程度のポスト頻度から始め、フォロワーの反応を見ながら調整していくのが望ましいです。投稿の間隔を空けることで、ポスト一つ一つの価値が高まり、より多くのエンゲージメントを獲得しやすくなります。
次に、ポストのクオリティ管理についても注意が必要です。自動生成されるポストがすべて高品質であるとは限りません。ChatGPTは非常に優れた文章生成AIですが、時折意図しない内容を生成してしまうことがあります。事前にプロンプトをしっかり設定し、AIが作成する内容の方向性を明確に伝えることが大切です。
また、定期的にポスト内容を手動で確認し、質を保つことが欠かせません。特にビジネスアカウントの場合、ブランドのイメージにそぐわない投稿が自動で発信されてしまうリスクがあります。そのため、少なくとも週に一度は自動ポストの履歴をチェックし、必要に応じて修正を加えるようにしましょう。
さらに、フォロワーとのエンゲージメントも自動化だけに依存しないように注意しましょう。SNSの本質は双方向のコミュニケーションです。自動ポストを設定していても、フォロワーからのリプライやダイレクトメッセージには、できるだけ手動で返信するように心がけるべきです。自動投稿だけではフォロワーとの関係が一方通行になりがちで、信頼関係が築きにくくなります。
エンゲージメントを高めるための工夫として、自動投稿と手動投稿を組み合わせる方法があります。例えば、ChatGPTで生成した情報提供系のポストを自動化しつつ、リプライへの返信やフォロワーの投稿に対するリアクションは手動で行うようにすれば、より人間味のある運用ができます。
また、自動化の内容は定期的に見直すことも重要です。Xのアルゴリズムは定期的にアップデートされており、自動化のやり方が古くなると効果が薄れてしまう場合があります。特に、ハッシュタグの使用や投稿の最適なタイミングなど、運用データを分析して改善を続けることが必要です。
ハッシュタグの使い方も注意が必要です。ChatGPTに「ハッシュタグを自動生成してください」と指示することは可能ですが、過剰に多くのハッシュタグを付けると、逆に投稿の信頼性が低下することがあります。目安としては1回のポストにつき、2〜3個のハッシュタグが適切です。
次に、投稿の一貫性にも気を配りましょう。Xの自動化を行う場合でも、投稿のテーマやスタイルを統一することが大切です。例えば、ある日はビジネスの話題で次の日は全く関係ないジョークポストというようにバラバラな内容だと、フォロワーが混乱してしまうことがあります。ChatGPTに対して、「〇〇に関する投稿を生成してください」とテーマを固定して指示するのがおすすめです。
さらに、自動化の際には著作権や倫理面にも注意が必要です。AIが生成した文章であっても、他者のコンテンツをそのままコピーしたような内容にならないよう注意しなければなりません。ChatGPTが参照した情報がどこから来ているのかを完全に把握できない場合があるため、特にニュース記事の要約などをポストする場合には、自分で一度内容を確認し、独自の表現を心がけることが大切です。
また、感情的になりすぎる内容や、攻撃的なポストの自動化は避けましょう。SNSでは一度投稿した内容がすぐに拡散されるため、炎上リスクを避けるためにも、ポジティブで有益な情報発信を心がけるべきです。
定期的なパフォーマンス分析も忘れずに行いましょう。Makeでは、シナリオの実行履歴を確認できる機能があるため、どのポストがどの程度のエンゲージメントを得られたかを確認できます。効果が高かった投稿のプロンプトを保存しておき、低パフォーマンスの投稿は改善していくと、より効率的な運用が可能になります。
最後に、自動化を導入する際は、無理にすべての投稿を自動化しようとせず、まずは一部の投稿から試してみるのがよいでしょう。例えば、週に数回のニュースまとめや、月曜の朝にモチベーションアップの名言を投稿するなど、特定のテーマから始めてみるのがおすすめです。慣れてきたら徐々に自動投稿の範囲を広げ、自分のアカウントに最適なスタイルを見つけていきましょう。
このように、自動化の便利さを最大限に活かしつつ、注意点をしっかりと押さえることで、Xの効果的な運用が可能になります。自動化ツールは上手に使えば非常に強力な味方になりますが、運用の目的やフォロワーとのつながりを大切にしながら活用していくことが成功のカギとなります。
まとめ
ChatGPTとMakeを活用してX (旧Twitter) を自動化する方法を解説しました。これにより、日々のポスト作成や投稿の手間を大幅に削減できるだけでなく、継続的で効果的な情報発信が可能になります。
今回紹介した手順は以下の通りです。
- MakeとChatGPTのセットアップ
- OpenAIのAPIキーを取得しMakeに登録
- Xアカウントとの連携設定
- 自動投稿のスケジュール設定
この方法を活用すれば、SNS運用が劇的に効率化され、より本質的なマーケティング活動に集中できるでしょう。ぜひ、この記事を参考にして、Xの自動化にチャレンジしてみてください。