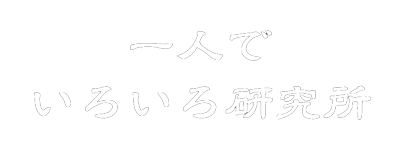身内のお葬式で関係者から「香典」という金品を頂くことがあり、挙げた側はお礼状と香典返しをしなければなりません。しかし、初めてだと金額や手紙に何を書けば良いのか分からない人も多いでしょう。そんな人のためにお礼状の書き方と香典返しのマナーや相場について解説します。
香典返しのお礼状の書き方
そもそも「香典」というのは、亡くなった人の霊前に供える金品のことです。自分や故人の会社などの関係者、遺族の配偶者の実家の人等から遺族に手渡されます。香典返しは、その頂いたご香典のお返事ということになります。
香典返しはお礼状というお手紙と一緒に送ります。お返事としてのお礼状なのですから当然ご香典を頂いた事と香典返しを差し上げることを書くことになりますが、具体的に何を書けば良いのでしょうか。
香典返しのお礼状の書き方のポイント一覧
【香典返しに添えるお礼状の書き方のポイント】
| 書く内容は「ご香典のお礼」「法要を終えた報告」「略儀で済ませることへのお詫び」「香典返しを受け取ってほしいというお願い」 |
| お礼状のお手紙は、葬儀の形式の宗教・宗派、または地域に合った言葉を使う |
| 香典返しのお礼状のお手紙は「拝啓」「敬具」を使う |
| 忌中・喪中の期間に香典返しをする場合はその点について一言添える |
| 本文の後ろに書く日付は法要・五十日祭・記念祭を行った日(年月のみに書く書き方もある) |
| 香典返しのお礼状の書き方に不安があるなら業者のサービスを使うのが安心 |
香典返しのお礼状を書く前に確認しておきたい書き方のポイントを挙げました。具体的な内容は文例で紹介しますが、お礼状のお手紙はお返事とはいえ長々と書かずに短めにします。
またここでは仏教式の「法要」と書きましたが、お葬式の宗教によってこの後執り行う行事の名前が違います。神道式なら「五十日祭」、キリスト教式なら「記念祭」や「追悼ミサ(カトリック)」または「記念集会(プロテスタント)」という名前で書きましょう。
香典返しのお礼状は正式なお返事なので、形式もお手紙やはがきが主流ですが、時代の変化によりメールで書く形式も増えてきています。ただ葬儀は人生最大の儀式の一つであり、それに関する香典返しのお礼状は紙を使ったお手紙で出す方が無難でしょう。
最優先なのは香典を頂いた事へのお礼
ご香典へのお返事なので、お礼状には「香典を頂いたお礼」が最優先となります。これを前置きの後一番に書くべきです。お礼状なので当然ですが、感謝すべきは金額ではなく香典を下さった方のお気持ちです。
また香典返しに添えるお礼状は「お手紙でのご挨拶になってしまうことへのお詫び」と「香典返しを受け取るお願い」も必須となります。昔の香典返しは実際に一軒一軒挨拶をしましたが、現代ではそうもいきません。ですが何のお断りもなくお手紙だけで済ますのも無礼なので、礼儀としてこれらのお断りの言葉を添えるようにしましょう。
香典返しの相場や金額
香典返しのお礼状の書き方の基本は分かりましたが、実際の香典返しとして送る品物はどのような金額のものが相場なのでしょうか。香典によっては会社単位でまとめられているものもありますし、非常に悩ましいところです。
香典返しの相場はある程度決まっており、送る品物もお菓子や商品券といったいわゆる「消耗品」が多いです。頂いた金額に見合った品物を送りましょう。
香典返しの相場は一般的に「半返し」か「3分の1返し」
香典返しは、「半返し」か「3分の1返し」でお返事するのが相場と言えます。たとえばご香典として3万円を受け取った場合、「半返し」なら1万5千円相当の品物を、「3分の1返し」なら1万円相当の金額の品物をその送ってくれた人に送るという意味です。実際は「半返し」でお返しをする場合が多いでしょう。
またご香典とは別に生花を送ってくれた人には、相手にもよりますが少し予算を上げた品物で香典返しするのが良いとされています。特に会社の上司や親しいお友達には料金を上げておくと良いでしょう。式を手伝ってくれたり協力してくれた人にも、千円くらいの予算でお菓子や簡単な品物をお返ししておきたいところです。
会社からのご香典に香典返しは必要?
お葬式によっては会社単位でご香典が届くこともあります。その場合お返事として香典返しすべきか悩む人もいるでしょう。結論から言うと、香典返しするかどうかは会社の社風によって変わります。
どこの部署から出るかは会社によって違いますが、形式として総務課から出た場合、香典返しはしなくても良いです。会社関係でも親しい人から頂いた場合はお返しする方が良いでしょう。
会社にもお返しするなら、金額にもよりますが皆で分け合えるお菓子やお茶がおすすめです。もしご香典の金額が個々から頂いでもおかしくない金額であれば、一人ずつ香典返しの品物を用意した方が良いでしょう。
香典返しのお礼状の文例
次に、香典返しのお礼状の文例を考えてみます。先に書き方として書く内容を解説しましたが、この項では具体的に何を書けば良いのかについて、お礼状の文例をより深く見ていくこととします。お葬式の形式によって香典返しのお礼状に書く言葉も若干違うため、事前に調べておくのがおすすめです。
短文以外で宗教を問わないテンプレートとして使える文例も用意しました。宗教によっては単語を変えた方が良い場合もありますが、実際に香典返しのお礼状を書く際の参考にしてみて下さい。
香典返しのお礼状の文例
【仏教式のお葬式・香典返しの場合の文例】
| おかげをもちまして この度 (戒名) 四十九日法要を滞りなく営むことができました |
【神道式のお葬式・香典返しの場合の文例】
| おかげをもちまして五十日祭を滞りなく済ませることができました |
【キリスト教式のお葬式・香典返しの場合の文例】
| 本日〇日 記念祭を相済ませました |
香典返しに添えるお礼状の内容は、お葬式の宗教・宗派によって使う言葉が若干違います。仏教では個人の戒名を記しますし、本来ご香典の文化がないキリスト教ではご香典のことを「御花料」と書きます。お葬式で用いられる死生観や文化は宗教によって大きく違いますので、書く前に必ず調べておきましょう。
テンプレートとしても使える香典返しの文例
【どの宗教でも使える香典返しのお礼状の文例】
| 拝啓時下ご清祥のこととお慶び申し上げます。先般 (続柄・故人名) 永眠の際につきましては 多くのお気遣いとご香典を賜り 誠にありがとうございました生前 親しくされておりました皆様にお見送りいただき 故人もさぞ喜んでいることと存じますつきましては 供養のしるしとして心ばかりの品をお届けいたしますので ご受納くださいますようお願い申し上げます本来であればお目にかかりお礼を申し上げるべきところ失礼ではございますがまずは略儀ながら書中をもってお礼かたがたご挨拶申し上げます敬具(平成)〇年〇月〇日(差出人名) |
どの宗教のお葬式の香典返しのお礼状・挨拶状のテンプレートとして使える文例です。神道なら「永眠」の部分を「帰幽」、キリスト教式なら「ご香典」を「御花料」と変えると良いでしょう。
香典返しのお礼状を送る相手によって、頭語と結語を変えるようにします。普段なら「拝啓」と「敬具」で良いですが、会社の上司や目上の人には「謹啓」「敬白」を使うと良いでしょう。
香典返しのお礼状のマナー
お葬式に関する死を扱う儀式は、マナーやタブーにかなり厳格な面があります。香典返しのお礼状も例外ではありません。マナーを犯してしまうと、人間関係にも影響が出かねません。
香典返しに添えるお礼状を書く際には、これから説明することに注意して書くようにしましょう。また、マナーとは少し違いますが、香典返しとお礼状はいつ送るのが良いのかについてもここで説明します。
香典返しのお礼状の書き方のマナー・注意点一覧
【香典返しの注意点】
| 句読点は使わないようにする(区切りは空白でつける) |
| 忌み言葉・重ね言葉は避ける(「重なる」という言葉も弔事ではタブー) |
| 手紙やはがきに手書きで書く香典返しのお礼状は縦書きで書く |
お葬式等の弔事で不幸が続くとして縁起が悪いとされる「忌み言葉」や「重ね言葉」を使うのはタブーですが、香典返しのお礼状も同じです。「益々」や「引き続き」といった、ついつい使ってしまいがちな言葉もありますので注意しましょう。
日常ならポジティブなイメージのある「次に」「生きる」といった言葉も、香典返しのお礼状では避けるべきです。どのような言葉が使えないのかを事前に調べておくことをおすすめします。
香典返しとお礼状はいつ送るべきか
香典返しは忌明けを告げる儀式の区切りという役割もあるため、基本的に忌明け後に送ります。仏教式のお葬式の場合は四十九日の法要、神道式なら五十日祭の後です。
一方ご香典と香典返し・忌明けは日本独自の文化で、西欧で生まれたキリスト教ではこれらの概念がありません。ですが、日本の社会ではキリスト教式のお葬式でも香典返しをするのが通例となっています。プロテスタントではお葬式から1か月後の昇天記念日、カトリックは30日後の追悼ミサ終了後に香典返しをしましょう。
現代では仕事等の関係上、忌明け前に香典返しをしてしまいたいという人もいます。その場合は忌明けを待たずに香典返しをしても問題ありません。しかし、その場合はお礼状に「早くお返ししたいと思いまして」と忌明け前に香典返しをしたことについて軽くお断りを添えるのが礼儀です。
お世話になった人にしっかりと感謝を伝えよう
香典返しのお礼状の書き方やマナー、相場について解説しました。最近はお葬式の形態も多様化しており、ご香典そのものをお断りする式もあるでしょう。それでもご香典やそのお返事となる香典返しという風習は根強く残っているため、最低限の知識は覚えておくと役に立ちます。
香典返しは個人を弔ってくれた人々に感謝の気持ちを伝えるものです。品物に添えるお礼状で、その想いをはっきりと伝えるようにしましょう。そうすることで、今後も自分と相手の関係を良好に保つことが出来ます。