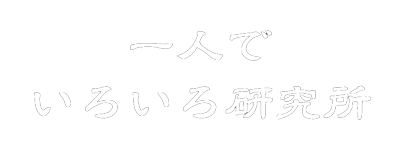秋から冬へと移り変わる11月、季語や11月の挨拶文とはどんなものでしょうか。11月初旬の季語、11月中旬の季語、11月下旬の季語と11月の挨拶文を例文をあげて解説します。11月の時期によって使う季語と挨拶文は変わってきますので学んでいきましょう。
11月の季語は?
「11月」に入ると、1年の終わりを感じ始めるようになります。「11月」は空気もひんやりし、日が暮れるのも日を追うごとに早くなり、夕方になればどこか物悲しい雰囲気が漂ってきます。
「11月」上旬には漂っていた秋の気配も、「11月」中旬、「11月」下旬と進むにつれて肌寒さも増し、季節は本格的な寒い冬へと移り変わっていきます。
ここでは「涼しい秋」から「寒い冬」へと移り変わっていく「11月」の「季節の言葉」や季節感溢れる「季語」を使った「11月」の秋の挨拶文を「11月」上旬、「11月」中旬、「11月」下旬と分けて解説していきます。
11月に使われる「季語」
「11月」は二十四節気では7日が立冬(冬の始まり)とされ、22日が小雪(雪が降り始める時期)となっているので、「11月」には冬を感じさせる「季語」もあります。
「11月」上旬は深まりいく秋の意味から深秋、紅葉、残菊、秋花などの「季語」、それが「11月」中旬になると晩秋、暮秋、初霜、落ち葉、そして「11月」下旬になると冬を感じさせる霜秋、向寒、夜寒、初雪などの「季語」が使われます。
他にもよく使われる「11月」の「季語」として、季秋、神無月、枯葉、冬日和、霜枯などがあり、秋が終わり、冬を間近に控えた「11月」の特徴をよく表しています。
自然に関する「季語」だけでなく、「11月」という季節の特徴から、自分で「11月」に食べる食べ物や行事などを参考に自分の「11月」の「季語」を作ってみるのも面白いかもしれません。
11月の時候の挨拶【上旬編】
「11月」上旬は暦の上ではまだ秋で空気もどこか暖かさを感じさせます。そんな秋の名残を感じさせる「11月」上旬の「季語」を使った時候の挨拶にはどんなものがあるのでしょうか。
通常、日本の手紙の書き方として、お礼状やはがきなどには、書き出しに「季語」や、その季節らしさを表現する「季節の言葉」を使った季節の挨拶、結びには相手を気遣う挨拶を書くのが普通ですが、手紙を出す相手によって書き出しを変える必要があります。
以下は「11月」上旬の書き出し挨拶文の例ですので、参考にしてしてみて下さい。なお、時候の挨拶の書き出しには拝啓と書くのが一般的です。拝啓は相手に対して敬意の意味を表しています。親しい間柄の人や友人には、拝啓と書く必要はありません。
11月上旬の一般的な挨拶(例文)
| 拝啓、向寒の候、お変わりなくご健勝のこととお慶び申し上げます。 |
| 拝啓、秋も深まり、めっきり日脚も短くなってまいりました。お変わりございませんか。 |
| 拝啓、立冬とは申せ、おだやかな秋日和が続いております。いかがお過ごしでいらっしゃいますか。 |
ここで使われている「11月」上旬の「季語」は向寒、立冬。
11月上旬のビジネス上の挨拶(例文)
ビジネス上の時候の挨拶には、「季語」以外のところの挨拶文には以下のような雛形や定型文がありますので、それに「11月」上旬の「季語」をつけるのが一般的です。
| 拝啓、○○の候、平素は格別のご高配を賜り、心より御礼申し上げます。 |
| 拝啓、○○の候、貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。 |
| 拝啓、○○のみぎり、貴社いよいよご発展の段、お慶び申し上げます。 |
| 拝啓、○○のみぎり、皆様、益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。 |
| 拝啓、○○のみぎり、○○様におかれましてはお元気でご活躍のことと存じます。 |
○○のところに「11月」上旬の「季語」、晩秋、菊花、錦秋、秋冷、霜秋等を入れます。
11月上旬の親しい間柄の人への挨拶(例文)
| 日毎に秋の深まりを感じます。お元気でお過ごしですか。 |
| 日脚がかなり短くなってきました今日この頃です。お元気でいらっしゃいますか。 |
| 秋も深まり、紅葉に目を奪われる季節になりました。お元気ですか。 |
| 落ち葉いっぱいのこの季節、いかがお過ごしでいらっしゃういますか。 |
| 冬の訪れを少しづつ感じつつも、穏やかな秋日和が続いております。皆様お変わりありませんか。 |
ここで使われている「11月」上旬の「季語」は紅葉、落ち葉、秋日和。
11月の時候の挨拶【中旬編】
「11月」は暦の上では7日から冬ということになっていますが、「11月」も10日を過ぎると、暖かいと感じる日は少なくなり、空気も冷たさを増し、冬の到来を感じさせる「季語」を使った挨拶が季節感に合います。
「11月」中旬の挨拶を、一般的な場合、ビジネス上の場合、親しい間柄の人への場合と3パターンに分けて書き出しの挨拶文を紹介します。
「11月」中旬の一般的な挨拶(例文)
| 拝啓、初霜の便りも聞かれる今日この頃、ますますご壮健のことと存じます。 |
| 拝啓、吐く息も日に日に白くなり、朝夕の冷え込みも厳しさを増してまいりました。 |
| 拝啓、枯葉もすっかり落ち尽くし、冬の到来を感じさせる今日この頃です。 |
| 拝啓、肌寒さが身に染みる立冬の折、お元気でお過ごしでいらっしゃいますでしょうか。 |
ここで使われている「11月」中旬の「季語」は初霜、枯葉、立冬。
「11月」中旬のビジネス上の挨拶(例文)
「11月」上旬の時候の挨拶同様、決まった雛形や定型文に「11月」中旬の「季語」を入れます。
| 拝啓、○○の候、貴社ますますご隆盛のことと心よりお慶び申し上げます。 |
| 拝啓、○○の候、貴社におかれましては、ますますご発展のことと存じ上げます。 |
| 拝啓、○○の候、皆様におかれましては、お変わりなくお仕事にご精励のこととお慶び申し上げます。 |
| 拝啓、○○のみぎり、○○様におかれましては、日々活躍の段、お慶び申し上げます。 |
| 拝啓、○○のみぎり、冷気が増し、身心引き締まる今日この頃、皆様におかれましてはお元気でご活躍のことと存じます。 |
○○のところに「11月」中旬の「季語」、立冬、落葉、初霜、冷雨、深冷などを入れます。
11月中旬の親しい間柄の人への挨拶(例文)
| 暦の上では冬となり寒くなってきました。お元気でいらっしゃいますか。 |
| 落ち葉を落とした木々の姿に一抹の寂しさを感じる今日この頃です。 |
| 時雨の季節になりました。気高く咲いている花の姿に募秋の儚さを感じます。 |
| 七五三の季節です。近くの神社は小さい娘さんの可愛い着物姿で賑わっています。 |
| 木枯らしの冷たさが深まり行く秋を感じさせます。 |
ここで使われている「11月」中旬の「季語」は落ち葉、時雨、七五三、木枯らし。
11月の時候の挨拶【下旬編】
「11月」下旬になれば冬はもう目の前です。「11月」下旬に使う枕詞は「雪」や「霜」など本格的な冬の到来を間近に感じさせる「季語」が多くなってきます。
「11月」下旬の一般的な挨拶(例文)
| 拝啓、小雪が過ぎ、冬が間近に迫ってまいりました。お元気でいらっしゃいますか。 |
| 拝啓、十一月も終盤に入り、冬の訪れを身近に感じます。お変わりなくお過ごしでいらっしゃいますでしょうか。 |
| 拝啓、霜枯れの寒さを感じ始めるこの季節、皆様、お元気でお過ごしでしょうか。 |
| 拝啓、朝夕の冷え込みが肌を突き刺します。いかがお過ごしでいらっしゃいますか。 |
ここで使われている「11月」下旬の「季語」は小雪、霜枯れ。
「11月」下旬のビジネス上の挨拶(例文)
「11月」上旬、「11月」中旬同様、以下の決まった定型文や雛形に「11月」下旬の「季語」を入れます。
| 拝啓、○○の候、御社、ますますご隆盛のこととお慶び申し上げます。 |
| 拝啓、○○の候、貴社におかれましてはいよいよご発展の段、お慶び申し上げます。 |
| 拝啓、○○の候、○○様におかれましては、ご清祥のことと心よりお慶び申し上げます。 |
| 拝啓、○○のみぎり、皆様ますますご健勝のことと存じ上げます。 |
| 拝啓、○○のみぎり、皆様におかれましてはますますお仕事にご精励の段、お慶び申し上げます。 |
○○のところに「11月」下旬の「季語」は小雪、霜月、霜寒、向寒、夜寒等を入れます。
11月下旬の親しい間柄の人への挨拶(例文)
| 寒風に冬の到来を感じる季節となりました。 |
| 暖かい缶コーヒーにぬくもりとおいしさを感じ始めた今日この頃です。 |
| 鍋料理が嬉しくなる季節です。 |
| 夜の風景の色濃さと吐く息の白さで冬の訪れを感じます。 |
| 夜風の寒さが身に沁みます。お元気ですか。 |
| 最近、本当に寒くなってきましたね。元気にされていますか。 |
ここで使われている「11月」下旬の「季語」は寒風。
「11月」の手紙の書き出し/結語を学ぶ
手紙は頭語と結語は一つのセットになっています。通常、手紙の書き出しは拝啓で始まり、結びの結語は敬具で終わります。
手紙の書き出しは、「11月」初旬、「11月」中旬、「11月」下旬に応じた「季語」や季節を感じさせる枕詞を使った挨拶で書き始め、書き終わりには相手を気使う挨拶を書き、最後は敬具でしめくくります。
なお、女性の場合は敬具の代わりに「かしこ」を使っても構いません。
「11月」の手紙の結びの挨拶(例文)
「11月」の結びの挨拶も、「一般的な挨拶」、「ビジネス上の挨拶」、「親しい間柄の人への挨拶」と「11月」らしさを出して簡単にまとめてみました。
「11月」の一般的な結びの挨拶(例文)
| 向寒のみぎり、お風邪には気をつけてお過ごし下さい。敬具 |
| 気候不順な折、末筆ながら皆様のご健康とご多幸をお祈り申し上げます。敬具 |
| 季節の変り目、お体ご自愛下さい。敬具 |
| 冷気が厳しくなってまいりましたが、風邪などひかれないようご注意下さい。敬具 |
「11月」のビジネス上の結びの挨拶(例文)
ビジネス上の結びの挨拶で「11月」の枯れた「季語」を使うと、マイナス的なものを暗示させますので、特に「季語」を使って結ぶ必要はなく、相手の社業の発展や仕事の成功を願う文章で締めくくるのが普通です。
| 社業のますますのご発展を心よりお祈り申し上げます。敬具 |
| 御社の更なるご活躍とご発展を祈念しております。敬具 |
| ○○様におかれましては、何かとご多忙とは存じますが、お体の方ご自愛下さい。敬具 |
| ○○様の今後のより一層のご活躍をお祈り致しております。敬具 |
「11月」の親しい間柄の人への結びの挨拶(例文)
| 今は季節の変り目ですので、風邪などひかれないよう気をつけて下さい。 |
| 寒い冬はもうすぐですが、体調など崩されないようお気をつけ下さい。 |
| 冬支度で何かとお忙しいとは思いますが、健やかにお過ごし下さい。 |
| 師走はもうすぐです。食べすぎ、飲みすぎには注意して下さい。 |
| 年末、年始の休みの日、お会いできるのを楽しみにしております。 |
秋の季節の挨拶文まとめ
秋は夏から冬へと移り変わっていく季節です。
9月はまだ夏の名残があり暑さも残っていますが、10月になると木々は紅くなって気候は涼しくなり、「11月」になると枯葉が地面に舞い降り、空気も冷たくなってきます。
そんな移り変わりを感じさせる9月、10月の時候の挨拶を見ることで「11月」という秋の最終月の季節感を考えてみるのも一興です。
9月の時候の挨拶(例文)
| 厳しい残暑が続いておりますが、お元気でお過ごしでいらっいますか。 |
| 残暑もようやく和らいでまいりました。いかがお過ごしですか。 |
| 澄んだ空の高さに秋を感じるようになりました、ご家族の皆様はお元気でしょうか。 |
| 朝夕、めっきり涼しくなり、過ごしやすくなってまいりしたがお変わりませんか。 |
| 爽やかな秋風が心地良いです。皆様におかれましてはお元気でお過ごしのことと存じます。 |
「11月」と比べると夏の名残が強い挨拶文です。
10月の時候の挨拶(例文)
| 秋晴れの爽やかな日が続いておりますが、お変わりなくお元気でいらっしゃいますか。 |
| うららかな小春日和が続いております。ご家族の皆様はお元気でしょうか。 |
| 秋晴れの心地良い季節となりました。○○様におかれましてはご健勝のこととお慶び申し上げます。 |
| 秋が深まってまいりました。そちらの紅葉はいかがですか。 |
| 朝夕、冷え込んでまいりました。皆様におかれましてはお変わりなく嬉しく存じます。 |
「11月」と比べると涼しさが感じられる挨拶文です。
儚さを感じる11月
秋はどこか物悲しさが漂う季節です。
賑やかな生命力に溢れた夏が過ぎると、日が暮れるのもだんだん早くなり、木々も紅くなって「11月」に入るとやがて葉は落ちていきます。そこに自然の息吹が終わりに向かって行くのを感じるので、どこか空しさや儚さを感じるのではないでしょうか。
特に「11月」は秋の最終月でもあるので、切ない感じはいっそう強くなります。そのような寂寥感、物悲しさは昔詠まれた俳句の中にもよく表れています。
「11月」に詠まれた俳句を参考にして自分で色々「11月」の時候の挨拶を手紙に書いてみるのも楽しいでしょう。
11月の俳句 「季語」
俳句は「季語」を必ず一つ使って詠むということがルールになっています。「季語」は俳句にとってはそれぞれの季節感を表すとても重要なもので、季節ごとの醍醐味や季節らしさを表します。
「11月」の俳句で詠まれた自然を題材にした「季語」には、木枯らし(こがらし)、時雨(しぐれ)、山茶花(さざんか)、初霜(はつしも)、落葉(おちば)、初氷(はつごおり)などがあります。
晩秋から初冬の「11月」の俳句には寂寥を感じつつも、その寂しさや悲しさの中に喜びや人生の意味を見出そうとする古人の気持ちがうかがえます。
「11月」 寂寥感のある俳句(例文)
| 世の中も 淋しくなりぬ 三の酉(正岡子規) |
| 初霜に 負けて倒れし 菊の花(正岡子規) |
| 母親を 霜よけにして 寝た子かな(小林一茶) |
| かへり花 暁の月に ちりつくす(与謝野蕪村) |
| 木枯らしの 吹き行くうしろ すがたかな(服部嵐雪) |
| 百歳の 気色を庭の 落葉哉(松尾芭蕉) |
ここで使われている「11月」の「季語」は三の酉、初霜、霜、暁の月、木枯らし、落葉。