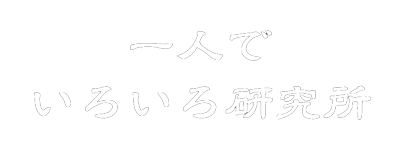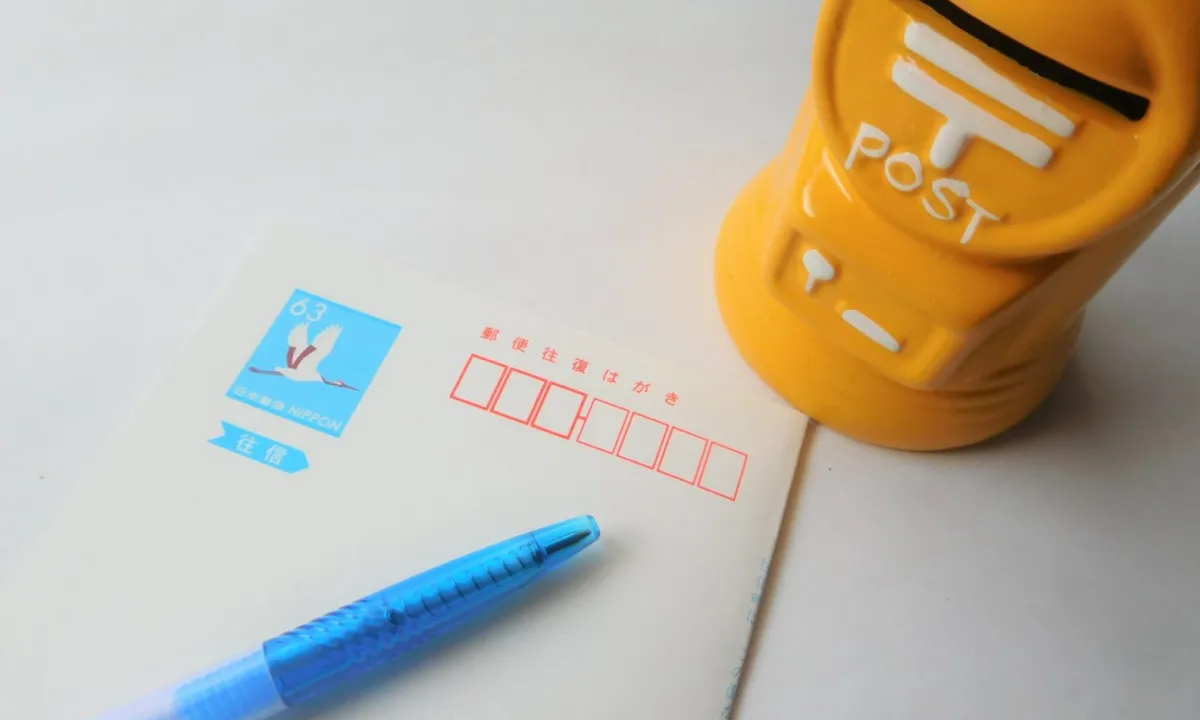往復はがきは今までに何度か使ったことがあるでしょう。でも、書き方についてきちんと教わったことはあまりないのではないでしょうか。今回は往復はがきについて書き方やマナーについて少し詳しく説明しますので、是非実際に役立ててください。
往復はがきの仕組み
まず、往復はがきの仕組みについて説明します。
往復はがきの仕組み
往復はがきは、差出人が相手に送る文面が書かれた「往信用はがき」と、その返事を出すための「返信用はがき」が一続きの1枚の用紙で作られています。
往復はがきを送るときは、相手の宛先が表になるように折って投函します。相手が受け取ったら、真ん中で切り離し、「返信用はがき」に返信の文面を書いて差出人へ送ります。
往復はがきは、真ん中で切り離してみると、二つのはがきが連結されていることがわかります。つまり、受取人の宛先が書かれた方のはがきの裏側には差出人の文面が書かれています。
そして差出人の宛先が書かれた方のはがきの裏側には、受取人が書く文面のスペースがあります。
今度は切り離さない状態でもう一度説明します。返信用はがきを受取人の宛先が書かれた面を上にして広げてみると、真ん中から左半分が受取人の宛先が書かれており、右半分が受取人が返事を書く面になります。
これを裏返しにすると、左半分が差出人の宛先が書かれており、右半分が差出人からの文面になっています。
仕組みの図示
往復はがきを広げた状態で、下記のような位置関係になっています。
| 受取人の住所氏名 (往信) 差出人 | 受取人が返事を書く面 (返信) |
| 差出人の宛先 (返信) | 差出人からの文面 (往信) |
往復はがきの使い方
ビジネスやプライベートでもよく使われる、往復はがきの使い方を説明します。
往復はがきの使い方
往復はがきは、差出人が受取人に、例えば同窓会の出欠の可否を回答してもらいたい場合などに使用します。このほかに、パーティの招待状、結婚式の案内、ビジネスでは、商品を買った時の特典への応募用などに使用されます。
返信用の面には、あらかじめ差出人宛の住所氏名を書いておき、またその裏側には返信の回答がしやすいように文面を書いておきます。そのため、受取人は回答を書いて、真ん中から切り離せば、そのまま返信ができます。
前述のように往復はがきは、往信と返信がひと続きの1枚になっています。前項の図で示したように、往信(受取人の住所氏名が書かれている面)の裏は往信のメッセージが書かれています。
往信(受取人の住所氏名が書かれている面)の右側には返信のメッセージを書く面があります。この返信の面のすぐ裏側には差出人の住所氏名が書かれています(返信の際の宛先になります)。
このような構造になっていますので、真ん中から切り離せば、左側が1枚の往信のはがきになり、右側が返信の1枚のはがきになるわけです。
したがって、往復はがきを受け取った人は、往信のメッセージを見てから返信の回答を書き、真ん中から切り離して返信のほうを投函します。
なお、郵政はがきの往復はがきは、往信の宛名面には水色の切手が印字されており、返信の宛名面には緑色の切手が印字されています。返信の時には、緑色の切手が印字してあるほうであることを確認しましょう。
往復はがきの書き方
差出人が、往復はがきを出す場合の書き方を説明します。
往信の宛名面の書き方
| 往信の宛名面 | 送り先の宛名を書きます。(なお、詳細は事項をご参照ください。) |
往信の文面の書き方
| 往信の文面 | 受取人の手元に残る文面です。挨拶の言葉と、会合等の内容および開催日時・場所、回答の締め切り日等を記載します。(後日、受取人がこの文面だけで会場へ行けるように必要な案内情報を記載しておきます。) |
返信の宛名面の書き方
| 返信の宛名面 | ここに書かれた住所・氏名のところに返信されます。通常は差出人の住所・氏名が書かれますが、ビジネス上の理由等で別の場所に返信させたいのでしたら、当該住所氏名を書きます。 なお、自分のところに返信してもらう場合は、名前の後に「様」などの敬称は書かずに、名前の下の左側に「行」や「宛」を書きます。 |
返信の文面の書き方
| 返信の文面 | 出席・欠席の確認や連絡事項など、受取人が回答を書きやすいように、あらかじめ「出席・欠席」のように記載しておきます。(「いずれかに○をつけてください」と付記しておきます。) |
往信の宛名の書き方
住所の書き方
| 住所 | 縦書きとします。書く位置は、郵便番号の4桁の四角枠の右側2つの中央に合わせると落ち着きがよくなります。 目上の人やビジネスのお客様の場合は、都道府県名から記載します。番地は漢数字を使用します。 住所を省略して書くと、マナー違反になりますので注意します。 |
ビル名・会社名の書き方
| ビル名・会社名 | 住所部分の文字よりも一回り小さな大きさで書きます。ビル名、マンション名は省略しないようにします。住所部分の書き始めよりも2文字分くらい下げて書き出します。 |
敬称と肩書きの書き方
| 敬称と肩書き | ビジネスで会社・団体の個人宛てにする場合は、社名や部署名、肩書きには敬称をつけません。名前の次に敬称(「様」が無難です。)を付けます。 ビジネス上、会社の部署宛の場合は、部署名のあとに「御中」を付けます。なお、御中を付けた後、個人名+「様」を付けると二重敬称になるのでビジネスマナー違反です。 |
往復はがきの送り方
それでは、往復はがきの送り方について説明します。
送り方について
往復はがきが書けたら、投函します。投函するときは、往信の宛名面と返信の文面が外側になるように、真ん中から二つに折るのが出し方です。(逆に往信の文面と返信の宛名面が内側になる出し方です。)
折っていないと「往復はがき」とはみなされないので出し方に注意します。
【注意】プリンターで印刷しやすいように、折っていない往復はがきも発売されています。招待状や同窓会の案内やビジネス等でたくさんプリンター印刷する出し方のときに便利です。
ただし出し方は、必ず真ん中で折ってから投函することを忘れないようにしましょう。
往復はがきを返信する際の注意点は?
返信の出し方の注意点を説明します。
返信の際の注意点
会合の案内状へ返信する場合の出し方を例に取り上げて説明します。返し方にもいろいろマナーがあります。
返信先の敬称の書き方
| 返信先の敬称 | 返信用の宛名には敬称が省略されており、代わりに名前の隣に「行」や「宛」と書かれています。これを二重斜線で消し、宛名の下に、個人宛の場合は「様」、会社や団体宛の場合は「御中」を書き足します。 |
自分の敬称の書き方
| 自分の敬称 | 「御出席」「御芳名」「お名前」「ご住所」の「御」「御芳」「お」「ご」の敬称を消します。一文字は斜めの二重線、二文字以上は縦の二重線で消します。結婚式は二重線ではなく、「寿」の字を重ねて消します。 |
出席の回答の書き方
| 出席の回答 | 出席に○を付け、「いたします」「させていただきます」とつなげます。 |
欠席の回答の書き方
| 欠席の回答 | 欠席に○を付け、「所用のため残念ながら欠席致します」などと書き添えます。やむを得ない理由で欠席する場合でも、あまり具体的に欠席理由を書く必要はありません。 |
返信の投函について
往復はがきを真ん中から二つに切って、返信のほうを投函するのが出し方です。最後にもう一度マナー通りに書かれているかチェックしましょう。
返信はできるだけすみやかにしましょう。返信の期限が書かれている場合は、十分期日に間に合うように余裕を持って投函するようにしましょう。
往復はがきを使う際のマナー
往復はがきを使用する際のマナーについて触れておきます。
往復はがきを使用し回答を求める際のマナー
往復はがきは、会合やパーティ等のお誘いと出欠の回答を求めるために利用されます。そのため、往復はがきを作成する際には、次の点に気をつけておくのがマナーです。
まず、会合等の内容や時間・場所・連絡先を明確に記し、また簡単な行き方の説明を添えると親切です。
また、幹事の連絡先、その他要望事項があれば記入お願いしますとも記載します。
返信の宛先が差出人とは異なる場合(宴会場に直接返信される場合とか)には、その説明を書いておくと親切です。
また、返信用の文面は、「出席・欠席」などのように○を付ければ済むように答えやすいレイアウトにしておくことも必要です。
往復はがきを有効に利用しましょう
多くの人に会合等の案内と出欠確認をする際には、往復はがきは便利なツールです。
受け取った人が読みやすく、また返信しやすいように工夫して出してあげれば、回答も早めにもらえるでしょう。
また、自分が往復はがきを受け取った時には、マナーに則って返信しましょう。
往復はがきを有効に利用すれば、会合の運営もスムーズに執り行え、楽しい思い出を作る一助になるでしょう。